中小製造業 モノづくり社長のための戦略的工場経営ブログ
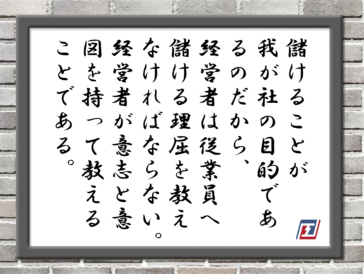
現場は利益を生み出す理屈を理解しているか?
1.利益率、損益分岐点比率、労働生産性 中小企業白書2021年度版には2019年度の中小企業収益実績値が掲載されています。各種指標の平均値や中央値です。我が社の水準が分ります。 ●売上高利益率売上高経常利益率を200...
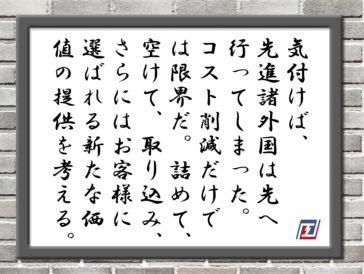
20年製造業労働生産性水準の国際比較
(1) 国民1 人当たりGDP の国際比較 毎年、12月に(公益財団法人)日本生産性本部から労働生産性の国際比較データが発表されます。昨年12月にも2020年データが発表されました。 グローバルでどの水準にあるのか知...
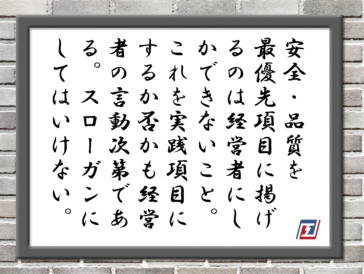
品質不正を未然に防ぐ唯一の方法
1.大手製造企業の品質不正問題 日経ものづくり2021年7月号では「日本の品質再定義」を特集しました。特集の中で2016年4月から2021年4月時点での品質問題事例を列記しています。 この5年間に深刻な案件だけでも4...
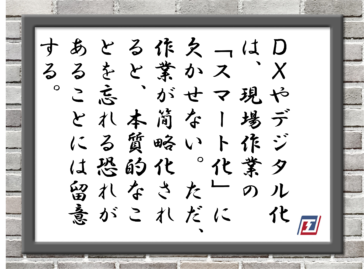
デジタル化であっても基本を忘れない
1.2020年版ものづくり白書 昨年発行された2020年版ものづくり白書の主題は下記です。「不確実性の時代における製造業の企業変革力」 世界は先が読めない様々な「不確実性」に直面しています。・経済安全保障をめぐる国際...
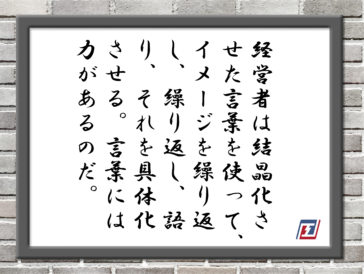
言葉を結晶化させて現場へ浸透させる
1.日本人を意識する機会 東京オリンピック、パラリンピックでは手に汗を握りながら応援した方も多かったのではないでしょうか? 「頑張れニッポン!」 日頃は気にしていない「日本人」を意識する機会でもありました。 ”私たち...
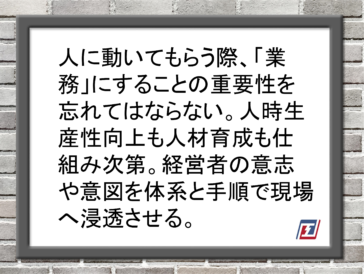
人時生産性向上も人材育成も仕組み次第
1.人時生産性向上プロジェクトは結局、人材育成に行きつく 儲かる工場経営で目指すのは利益アップと給料アップの仕組みづくりです。 ご支援をしている経営者の方々とお話をしていると、多くの方が事業の持続的な成長とともに従業...
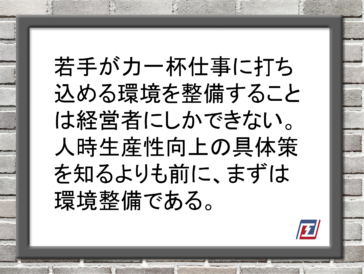
相手をリスペクトし仲間を賞賛する雰囲気づくり
1.日立製作所大みか事業所 日立製作所の大みか事業所では社会的インフラの情報システム開発、製造、保守を手がけています。生産品は制御盤です。その大みか事業所は2020年1月、世界経済フォーラムで世界の先進工場「ライトハ...
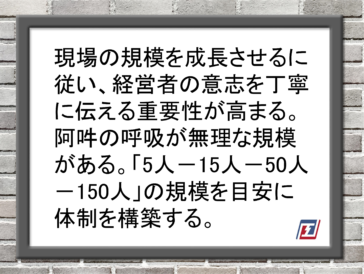
経営者は伝えたつもりになっていないか?
1.伝えたつもりになっていないか? 「経営者が考えているほどに現場は経営者のことを理解していない。」 ご支援先の現場でしばしば感じることです。経営者は自分の思いや意志を伝えたと考えています。しかし、現場は教えてもらっ...
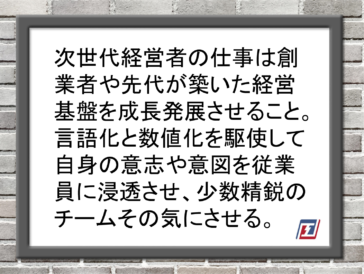
次世代経営者は〇〇で従業員を導く
1.創業者と2代目経営者の役割は違う 創業者と2代目経営者の役割は違います。創業者はゼロイチです。ゼロから事業をスタートさせます。試行錯誤の連続です。創業者も経験がないのでやってみないとわかりません。トライアンドエラ...
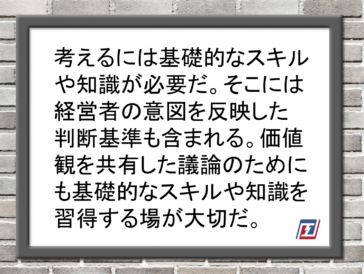
現場の基礎的なスキルや知識は低下していないか?
1.基礎的なスキルや知識の低下 モノづくりに関する技術者の基礎的なスキルや知識の低下は危機的なレベルになっている。このように考える技術者が多いようです。日経BPの「日経ものづくり」で実施したアンケートで明らかになりま...
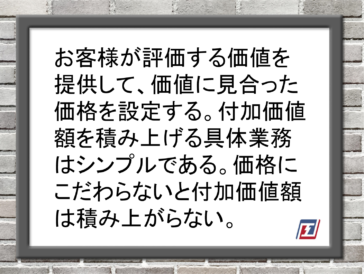
価格は下げるものだと思い込んでいないか?
1.価格は下げるものだと思い込んでいないか? 現場改革→意識改革→構造改革。儲かる体質に変える手順です。経営者は構造改革でさらなる付加価値額を積み上げたいと考えます。一方、時代の流れは少子化・人口減少、働き方改革です...
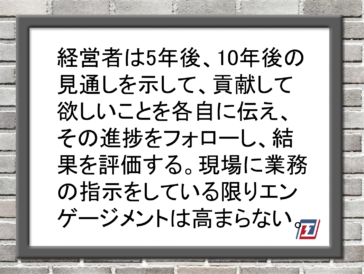
仕事のやり方を変えてエンゲージメントを高める
1.日本的経営3種の神器 高度成長期と平成バブルまでの経済成長を支えた日本的経営3種の神器と言われるものがあります。 ・終身雇用・年功序列・企業別労働組合 高度成長期とは戦後から1973年の第1次オイルショックの頃ま...
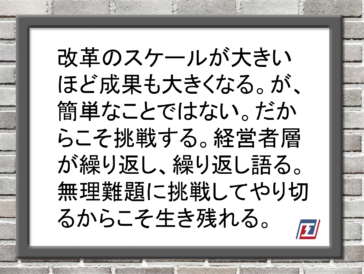
大きな改革は繰り返し語る事から始める
1.「トヨタ生産方式」大野耐一氏の言葉 トヨタ自動車元副社長、大野耐一氏の著書「トヨタ生産方式」には副題があります。「脱規模の経営を目指して」 「トヨタ生産方式」が出版されたのは1978年、今から43年前のことです。...
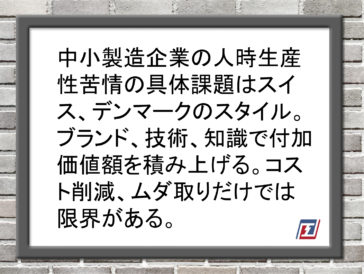
製造業労働生産性の国際比較
1.「労働生産性の国際比較2019」 日本生産性本部では毎年12月にOECDや世界銀行などのデータに基づいて世界各国の労働生産性を公表しています。2020年12月に「労働生産性の国際比較2019」が公表されました。 ...
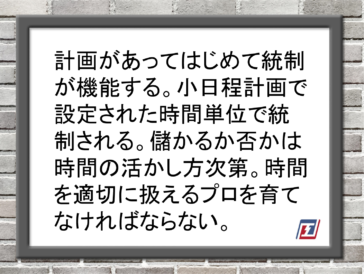
時間を適切に扱えるプロを育てる
1.「時間」は権威の象徴だった時代 「時間」は権威の象徴だ。このように考える時代がありました。660年、中大兄皇子(なかのおおえのみこ)が初めて漏刻を作り、人々に時刻を知らせたと日本書紀に書かれています。 漏刻とは水...
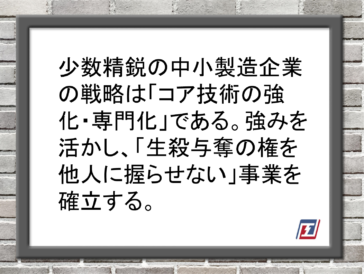
握られているのと握るのとでは雲泥の差
1.人時生産性150%へUP 中小製造企業はとにかく付加価値額人時生産性を高めたいのです。投入できる工数には制約があります。それでも付加価値額を積み上げて豊かに成長発展しなければなりません。 従業員とその家族の人生を...
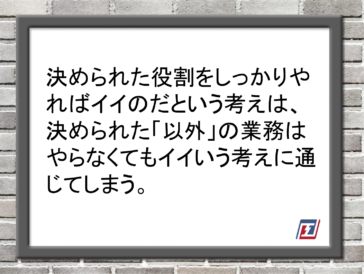
役割分担をやると現場で何が起きるか?
1.スカイマーク スカイマークは2015年1月に民事再生法適用を申請しました。伊藤も仕事柄しばしばお世話になる航空会社です。 そのスカイマークは、経営破綻後の危機的な状況の中、新たなことに挑戦してきました。部門を超え...
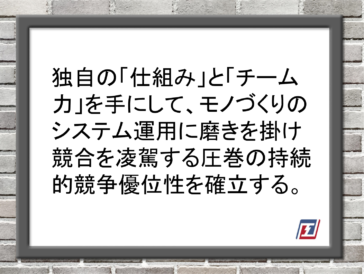
モノづくりのシステム運用に磨きを掛ける
1.巨大な赤字に直面している自動車業界 あらゆる産業がコロナ禍の影響を受けています。自動車業界も例外ではありません。主要自動車メーカー各社の2020年4月~6月期最終損益を見れば明らかです。 日産 2,855億円赤...
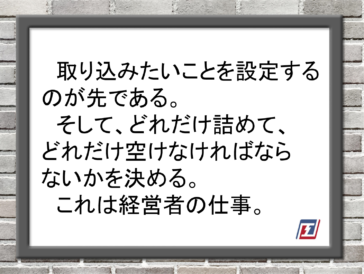
工数削減だけでは儲からない
1.「のぞみ」のコロナ対策と輸送能力アップ両立 8月7日より東海道新幹線で「のぞみ」を1時間に最大12本運転する「のぞみ12本ダイヤ」を設定するそうです。輸送能力が高まります。1本増やすと1300人アップです。1時間...

できない人に合わせるとどうなるか?
1.若宮正子さん 若宮正子さん(85歳)は高齢プログラマーとして知られている方です。プログラミングを独学で習得し、シニア向けのゲームアプリ「hinadan」をつくって、米アップルCEOのティム・クック氏から賞賛され...
