戦略的工場経営ブログ経営者は哲学を持って現場へ想いを繰り返し語る

ご自身の哲学を言語化できていますか?
1.所詮、他人は他人である
言うのは簡単ですけど自分のやりたいことを現場に落とし込むことは簡単ではない。 それが危機感としてあるので、こういう風に継続して発信しないと。 1回言っただけで分かってくれるほど人と人はつながっているわけではないんでね。本田圭佑選手の言葉です。 本田選手は小学生向けのスクールやクラブチームの実質的なオーナーでもあります。 サッカー選手と経営者の2足のわらじです。 先の言葉は、自身が所属しているイタリアの名門・ACミランのことを語ったものです。 好調とは言えない状況にあるのを受けて、経営者視点でチームの状況を説明しています。 工場経営も結局のところ人次第です。 人に働きかけて、動いてもらうことが経営の要諦です。 共感を醸成し、やる気を引き出し、自律性を発揮したくなる現場を整備すれば人は活きます。 最も理解し合った家族にさえ、自分の意図を正しく伝えるのは簡単ではありません。 会社の仲間は、理解しあっているとは言え、他人は他人です。 生まれた育った環境から始まり、学歴、職歴が、皆、異なります。 自分の意図することが、簡単に伝わると考える方が不自然です。 それ故に、多くの経営者は、自分の想いを現場へ浸透させるのに苦労します。 これこそが、経営者の仕事です。 ですから、想いが伝わったと実感できたときは、経営者ならではの充実感があるのではないでしょうか。 したがって、「現場が動かなくて困る」という趣旨の言葉を耳にすると違和感を感じます。 経営者の想いを現場に浸透させることこそが、経営者の仕事です。(出典:日本経済新聞2015年10月23日)
2.繰り返し語ることで本気度を示す
想いを現場へ浸透させるためには、繰り返し語るしかありません。 ひたすら繰り返します。 一方で、現場は、管理者や経営者の本気度を試してもいるのです。 「また、あんなことを言い始めた。 そのうち、あきらめて言うのをやめるかもしれないから、しばらく様子を見よう。」 繰り返し、繰り返し、繰り返し、現場へ語るのは、本気度を示すためです。 本気でやる遂げるぞ、と現場へ意思表示をしていることに他なりません。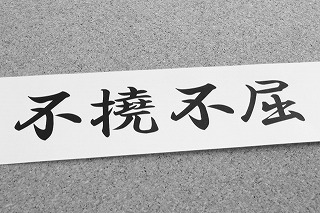 現場を引っ張るリーダーやトップが絶対にやってはならないことは、「やりっぱなし」です。
・言いっぱなし
・丸投げ
現場は「これは本気ではないな」と感じとります。
管理者や経営者が、そのつもりでなくてもです。
現場にそう感じさせてはいけません。
儲かる工場経営の根底を成す信頼関係が失われます。
絶対に避けたいことです。
しかしながら、想いを語り続けるのは、言うほど簡単なことではありません。
反応が鈍い現場へぶれることなく、語り続けるのには気力が必要です。
ただ、経営者であれ、管理者であれ、繰り返し語るしかないのです。
想いを伝えたいのなら、そうするしかありません。
仲間とは言え、現場の構成メンバーは「他人」だからです。
本気度を現場へ示す必要があります。
工場経営は、人に動いてもらってナンボノモノです。
現場を引っ張るリーダーやトップが絶対にやってはならないことは、「やりっぱなし」です。
・言いっぱなし
・丸投げ
現場は「これは本気ではないな」と感じとります。
管理者や経営者が、そのつもりでなくてもです。
現場にそう感じさせてはいけません。
儲かる工場経営の根底を成す信頼関係が失われます。
絶対に避けたいことです。
しかしながら、想いを語り続けるのは、言うほど簡単なことではありません。
反応が鈍い現場へぶれることなく、語り続けるのには気力が必要です。
ただ、経営者であれ、管理者であれ、繰り返し語るしかないのです。
想いを伝えたいのなら、そうするしかありません。
仲間とは言え、現場の構成メンバーは「他人」だからです。
本気度を現場へ示す必要があります。
工場経営は、人に動いてもらってナンボノモノです。
3.繰り返し語るためにたいせつなことは
生産現場の管理者時代、業績と安全衛生をセットで繰り返し、現場へ語っていました。 そうせざるを得ない状況に直面したからです。 半年に渡って、安全衛生上のトラブルを連続して発生させたときでした。 悪い流れを断ち切ろうと必死でした。 必死になって語っていれば、共感してくれる現場リーダーも現れるものです。 一緒に汗をかいてくれました。 そして、このような時であっても、現場には収益責任があります。 安全衛生上のトラブルでたいへんだろうから赤字で結構ですよ、とはならない。 当然のことです。 大手の現場なら、多くの役割を、多くの人員で分担できます。 負荷を分散させることが可能です。 しかし、経営資源に制約がある中小現場では、そうはいきません。 いきおい、管理者の業務上の負荷が高まります。 つらい状況になりますが、なんとかしなければなりません。 こうしたとき、ぶれずに、強い気持ちを持つためには、何かが必要です。 ふと一息ついたときに、素朴な疑問が、自然と湧き上がってきます。 ・なぜ頑張らねばならないのか ・なぜ想いを伝えねばならないのか こうした素朴な疑問に、圧倒的な確信を持って答えられる何かがなければなりません。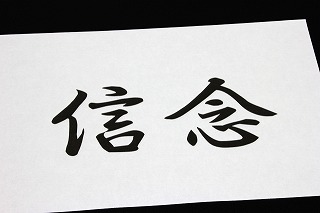 言い尽くされていますが、結局は「哲学」です。
「信念」です。
人生観、職業観、宗教観等、その人が長い人生を歩んだ結果、獲得した考え方。
これが仕事をする上で、最後の踏ん張りを生み出します。
当時、仕組みが未整備な職場でした。
将来への不安を口にする若手の人財もいました。
そこで、なんとか働き甲斐のある環境を整備したいとの想いが沸いていました。
若手は次世代を担う人財です。
新たな仕組みを作っては、その成果をいっしょに喜んでくれた現場でした。
彼ら、彼女らが、迷いなく、力一杯働ける環境が必要だとの想いがあったのです。
だから、管理者として頑張れました。
管理者や経営者が、自身の想いを繰り返し語れるのは哲学があるからです。
そして、仕事のやり方は哲学を反映します。
ですから、経営者は、自身の哲学を、会社経営に昇華させます。
経営者としての哲学=会社の哲学、つまり経営理念です。
何かコトを成し遂げようと考えるなら、ぶれないモノを持っていなければなりません。
儲かる工場では、哲学を精神論では考えません。
仕事を上手く進めるためのひとつの手順、テクニックと考えます。
山あり谷ありの人生を経た経営者は、なんらかの哲学を持ちます。
そして、その哲学を、漠然としたイメージのままではなく、言語化するのです。
言語化して自身のバックボーンにします。
行き詰ったときにも、ひと踏ん張りの気力が生まれます。
事業を成し遂げるためには、想いを繰り返し、繰り返し、現場へ語る地道な仕事が欠かせません。
現場の反応が悪かろうが、反発があろうが、繰り返し語ります。
そうして、共感を生み出さないと、他人を自律的に動かせません。
現場は、経営者や管理者の本気度を見ています。
意思を貫くための哲学です。
哲学の言語化で自身のバックボーンを形成し、繰り返し語る姿勢を貫きます。
その結果、経営者の想いが現場へ浸透するのです。
哲学があって、初めて、現場へ想いが浸透します。
哲学は、本田選手が経営で最も重視するものです。
先の言葉に引き続き、ACミランについて下記のように語っています。
言い尽くされていますが、結局は「哲学」です。
「信念」です。
人生観、職業観、宗教観等、その人が長い人生を歩んだ結果、獲得した考え方。
これが仕事をする上で、最後の踏ん張りを生み出します。
当時、仕組みが未整備な職場でした。
将来への不安を口にする若手の人財もいました。
そこで、なんとか働き甲斐のある環境を整備したいとの想いが沸いていました。
若手は次世代を担う人財です。
新たな仕組みを作っては、その成果をいっしょに喜んでくれた現場でした。
彼ら、彼女らが、迷いなく、力一杯働ける環境が必要だとの想いがあったのです。
だから、管理者として頑張れました。
管理者や経営者が、自身の想いを繰り返し語れるのは哲学があるからです。
そして、仕事のやり方は哲学を反映します。
ですから、経営者は、自身の哲学を、会社経営に昇華させます。
経営者としての哲学=会社の哲学、つまり経営理念です。
何かコトを成し遂げようと考えるなら、ぶれないモノを持っていなければなりません。
儲かる工場では、哲学を精神論では考えません。
仕事を上手く進めるためのひとつの手順、テクニックと考えます。
山あり谷ありの人生を経た経営者は、なんらかの哲学を持ちます。
そして、その哲学を、漠然としたイメージのままではなく、言語化するのです。
言語化して自身のバックボーンにします。
行き詰ったときにも、ひと踏ん張りの気力が生まれます。
事業を成し遂げるためには、想いを繰り返し、繰り返し、現場へ語る地道な仕事が欠かせません。
現場の反応が悪かろうが、反発があろうが、繰り返し語ります。
そうして、共感を生み出さないと、他人を自律的に動かせません。
現場は、経営者や管理者の本気度を見ています。
意思を貫くための哲学です。
哲学の言語化で自身のバックボーンを形成し、繰り返し語る姿勢を貫きます。
その結果、経営者の想いが現場へ浸透するのです。
哲学があって、初めて、現場へ想いが浸透します。
哲学は、本田選手が経営で最も重視するものです。
先の言葉に引き続き、ACミランについて下記のように語っています。
なぜ悪いかを分っていないような気がします。 気づかずにさまよっているんで選手としてやっていて難しさは続いています。 過去の栄光を捨て切れていないのか、昔と同じやり方でいけると思っているのか。 どちらにしてもフィロソフィーが感じられないというか。 一体感みたいないのが薄い感じはしますよね。 それ(フィロソフィー)がないと動物園になっちゃいますんでね。 会社が歩んでいく方向をしっかり社員全員に伝えることこそトップの役目だと思いますけどね。経営者が持つ哲学を経営理念に昇華させ、それが浸透したモノづくり現場は強いです。 現場は、経営者の想いを、自然と、肌で理解します。 経営者と現場が一体となった強さを感じます。 経営者は、哲学を持って、繰り返し、現場へ想いを語るのです。 経営者の哲学を経営理念に落とし込み、現場へ浸透させる仕組みをつくりませんか?(出典:日本経済新聞2015年10月23日)
