戦略的工場経営ブログ不断の変革で存続と成長を実現している老舗企業
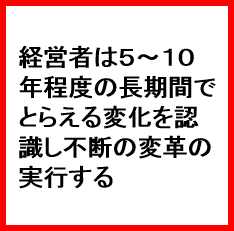
経営者は5~10年の長期の変化を認識し不断の変革の実行する、と言う話です。 5年先、10年先の見通しはありますか?
1.外部環境の変化を認識した。さて、次はどうする?
造るモノがない製造現場ほど寂しいものはありません。 リーマンショックや東日本大震災で稼働を停止した現場の雰囲気を思い出します。 売上高のめどが立たない状況で、現場のモチベーションを維持するのに苦労しました。 現場の生産活動に影響を及ぼす出来事は様々です。 業界動向のようにある程度、予測できること。 天災のように、予測不可能なこと。 いろいろありますが、経営者は、現場が受けるダメージを最小限にする努力を続けねばなりません。 外部環境変化への感度を上げること、そして対応力を強化することです。 ここで、南の島を想定します。 この島では、今、2つの問題を抱えています。 ・一時的なスコール(大雨)による水害 ・地球温暖化で徐々に潮位が上がってくることによる島全体の水没災害 両者の対応策は根本的に違います。 前者は、すでに問題が現実に認識されています。 被害も出ています。 緊急度は高いです。 すぐ手を打たねばなりません。 緊急を要しますが、対応策は考えやすい すでに被害が発生しているからです。 避難用の建物を島の各地へ建設すれば解決します。 一方、徐々に上がっている潮位への対応はそう簡単ではありません。 ・予測される潮位の上昇分、国土に盛り土して高さを増す ・島の住民全員が別の島へ引っ越しする など。 困難を回避するために、将来を見通す必要があります。 後者の問題への対応策は、時間を味方につけながら、島のトップがするべきものです。 戦略性を問われます。 後者の問題の特徴は、今、まだ、問題や支障は発生していないことです。 すぐに手を打たなくても、今は、困りません。 しかし、計画的に手を打たねばならない類の問題です。 対応の遅れを認識した時は致命的な状況に陥っています。 長期間でとらえる変化は”ゆでガエル状態”になる懸念があるのです。 「変化」を感知する際、外部環境の変化には2種類あることに留意します。
・1年~2年の短期間でとらえる変化
・5~10年の長期間でとらえる変化
1年~2年の短期間でとらえる変化は気が付きやすいです。
したがって、工場経営では5~10年の長期間の変化に注視します。
気が付いたら「水没していた」とならないようにしなければなりません。
5~10年の長期の変化は、変化のスピードが遅いため、気が付きにくいです。
しかし、事業活動の再定義が必要となる程の大きな変化になる可能性もあります。
そして、その変化への対応は経営戦略に密接に関係します。
意思決定は経営者にしかできません。
経営者の方が長期的な視野で変化を認識しました。
さて、次はどうするか?
2つのことを考えます。
1)既存事業を下記の3つに分類する。
・残すモノ ・変えるモノ ・捨てるモノ
2)将来の成長に向けて新たなモノを加える。
経営者は5年先、10年先を見据え、上記の選択をします。
つまり事業活動の再定義です。
「変化」を感知する際、外部環境の変化には2種類あることに留意します。
・1年~2年の短期間でとらえる変化
・5~10年の長期間でとらえる変化
1年~2年の短期間でとらえる変化は気が付きやすいです。
したがって、工場経営では5~10年の長期間の変化に注視します。
気が付いたら「水没していた」とならないようにしなければなりません。
5~10年の長期の変化は、変化のスピードが遅いため、気が付きにくいです。
しかし、事業活動の再定義が必要となる程の大きな変化になる可能性もあります。
そして、その変化への対応は経営戦略に密接に関係します。
意思決定は経営者にしかできません。
経営者の方が長期的な視野で変化を認識しました。
さて、次はどうするか?
2つのことを考えます。
1)既存事業を下記の3つに分類する。
・残すモノ ・変えるモノ ・捨てるモノ
2)将来の成長に向けて新たなモノを加える。
経営者は5年先、10年先を見据え、上記の選択をします。
つまり事業活動の再定義です。
2.環境変化へ対応して成長し続ける老舗企業の事例
ミツカンホールディングスは1804年創業の老舗の食品メーカーです。 「味ポン」で有名です。 祖業は食酢やポン酢ですが、20年近く前に本格参入した納豆も現在の稼ぎ頭です。 さらに14年6月には英欄ユニリーバから北米のパスタソース事業を2000億円超で買収しました。 その結果、2015年3月~8月期の連結売上高は1215億円と前年同期に比べ3割増えました。 海外比率は56%で前年同期対比13%増でした。 同社は200年以上の続いている老舗のブランドや伝統に安住していません。 新しい分野にも挑んでいます。 M&Aで海外進出も果たしています。 社内の人財は大いに活性化しているはずです。 創業家の8代目当主でミツカン会長の中埜和英氏は下記のように語っています。「永続的に企業活動を続けるのに 1番大切なのは、その時代の環境と身の丈にあわせて変えていくことだ。」米ゼネラル・エレクトリック(GE)もそうです。 同社も発明王トーマス・エジソンによる創業から100年以上の歴史を重ねています。 そのGEも事業内容を大胆に組み替え変革を続けています。 GEの利益の半分を稼いでいた金融事業からほぼ撤退しました。 また、伝統ある白物家電の事業を中国のハイアールに売却しています。 その一方で、仏重電大手アルストムを買収しています。 さらに、GEは「デジタル製造業」という新たな理念も打ち出しています。 情報通信技術を活用したインダストリアル・インターネットです。 (モノづくり工場でビックデータを活かす2つの着眼点) GEのジェフ・イメルト最高経営責任者は次のように考えています。 ”ネットによる革命が次は産業界にシフトする。” これまでネットにいる革命は消費者向け市場で起きていました。 それが、産業界でも起きると、GEのトップは予測しました。 GEは、デジタル化で製造業の生産性を高めるサービスを強化します。 (出典:日経新聞2016年3月8日)
 ミツカンホールディングスもGEも外部環境の変化を機会としています。
経営者自身が長期的な変化をとらえ、不断の変革を実行しているのです。
事業の取捨選択は経営者にしかできない重要項目です。
事業の再定義であり、存在意義の再定義です。
こうした戦略的意思決定に誤りがあってはなりません。
現状維持は「座して死を待つ」ことです。
しかし、一方で、誤った選択も企業の存亡に関わります。
経営者にもとめられるものは、長期的な展望で5~10年を見通す確かな目です。
ただし、不確実性の高い時代です。
情報を集めることは重要ですが、かならずしも、そこから正解を導けるわけではありません。
こうなると最後は、経営者の人生観や歴史観、会社をこうしたいという熱い気持ち次第。
「経営者の想い」次第となってきます。
現場やその家族が将来に向かって豊かな生活を送る状態を実現するのが目標です。
目指すべき状態の設定です。
この会社に入って幸せだったと感じてもらえる見通しを立てるのです。
そのために、外部環境に合わせた不断の変革をひたすら続けます。
貴社の5年先、10年先を見通す仕組みをつくりませんか?
まとめ。
経営者は5~10年の長期の変化に注目し事業の再定義をする。
経営者は5~10年の長期の変化を認識し不断の変革の実行する。
ミツカンホールディングスもGEも外部環境の変化を機会としています。
経営者自身が長期的な変化をとらえ、不断の変革を実行しているのです。
事業の取捨選択は経営者にしかできない重要項目です。
事業の再定義であり、存在意義の再定義です。
こうした戦略的意思決定に誤りがあってはなりません。
現状維持は「座して死を待つ」ことです。
しかし、一方で、誤った選択も企業の存亡に関わります。
経営者にもとめられるものは、長期的な展望で5~10年を見通す確かな目です。
ただし、不確実性の高い時代です。
情報を集めることは重要ですが、かならずしも、そこから正解を導けるわけではありません。
こうなると最後は、経営者の人生観や歴史観、会社をこうしたいという熱い気持ち次第。
「経営者の想い」次第となってきます。
現場やその家族が将来に向かって豊かな生活を送る状態を実現するのが目標です。
目指すべき状態の設定です。
この会社に入って幸せだったと感じてもらえる見通しを立てるのです。
そのために、外部環境に合わせた不断の変革をひたすら続けます。
貴社の5年先、10年先を見通す仕組みをつくりませんか?
まとめ。
経営者は5~10年の長期の変化に注目し事業の再定義をする。
経営者は5~10年の長期の変化を認識し不断の変革の実行する。
