戦略的工場経営ブログ感性と機能に注目した儲かる技術開発
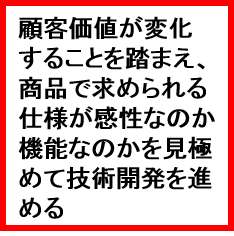
貴社の製品には、機能面のほかに、顧客へ提供している価値がありますか?
1.自動車部品を開発していたころに経験したこと
技術の進歩や時代の流れと共に、顧客価値を見直す必要があるのを実感したことがあります。 ティア1として自動車部品を自動車メーカーに供給する工場で勤務していたころの話です。 意匠性も求められる重要保安部品の開発業務に携わっていました。 車の基本性能は、走る、曲がる、止まるです。 不具合があると、この基本性能に支障をきたす恐れのある部品は、重要保安部品として扱われます、 その製品強度、性能が厳しく問われるのです。 一般的に、製品を厚肉に設計すれば、間違いなく強度仕様をクリアできます。 しかし、一方で燃費向上を目的とした、軽量化の要求も強くなってきていました。 競合先との軽量化競争が激しくなったのです。 新製品を開発するたびに競合の方が軽いとか、ウチが競争に勝ったとか。
軽量化競争が、しばしば話題に上がりました。
従来製法で、軽量化競争を勝ち続けることに限界を感じてきたのもこのころです。
そこで、競争力強化のため、新製法開発のプロジェクトが立ち上がりました。
そのプロジェクトは、試作を開始してから、約3年で実用化に至りました。
構想段階を含めると、もっと長期です。
アイデアが出されてから、約5年の月日を要しました。
そして、この技術は、実用化されて10年以上の年月が経過しています。
幸い、現在も、現役の量産技術として活用されています。(2016年時点)
こうした生産技術開発の中で、自動車部品に求められる仕様の変化を感じました。
軽量化競争の中、新たに固有振動現象への対応も求められる車種も出てきたのです。
従来製法で開発した製品を基準として軽量化が5%、10%と進んでいく中で、要求が強まってきました。
部品の軽量化が進んでいない時は、そもそも問題にはならなかった部品の剛性問題です。
軽量化、つまり部品の構成部材が薄肉になると、部品は変形しやすくなります。
その結果、製品全体の剛性が低下する問題に直面します。
製品の剛性が乗り心地や走行音に関係するとのことでした。
製品の固有振動値も設定数値以上との仕様が強調される状況に変わってきたのです。
エンジンやタイヤの静粛性が高まってきたことも背景にはありました。
単なる軽量化のみではなく、「剛性も維持できる薄肉化」。
こうした、律背反の技術課題に直面する場面が増えてきたことを思い出します。
軽量化を優先させて薄肉にすると、剛性が下がり固有振動値が下がる。
一方、剛性を優先させて厚肉設計すれば、
剛性が上がり固有振動値も上がって強度テストにもパスしやすくなるが、軽量化目標は達成できない。
軽量化と剛性を両立させるのに、日々、うんうん唸っていました。
その中で、さらに、意匠性を高める特殊塗装へのニーズも高まってきました。
当時扱っていた部品は、もともと意匠性も求められていた部品です。
見た目も重視、ではあったものの、
それまでは、よほどの特殊な用途でもない限り、特別な塗装を求められることはありませんでした。
カスタマイズカー向け部品などです。
それが、標準仕様の車種でも、意匠性を高めるために特殊塗料が求められるように変わってきたのです。
塗装技術を担当する技術部隊が、技術開発を進めました。
軽量化ニーズ ⇒ 軽量化+高剛性ニーズ ⇒ 加えて特殊塗装。
お客様が求めるニーズが変化してきました。
自動車を購入する最終顧客の嗜好が多様化すれば当然のことでした。
新製品を開発するたびに競合の方が軽いとか、ウチが競争に勝ったとか。
軽量化競争が、しばしば話題に上がりました。
従来製法で、軽量化競争を勝ち続けることに限界を感じてきたのもこのころです。
そこで、競争力強化のため、新製法開発のプロジェクトが立ち上がりました。
そのプロジェクトは、試作を開始してから、約3年で実用化に至りました。
構想段階を含めると、もっと長期です。
アイデアが出されてから、約5年の月日を要しました。
そして、この技術は、実用化されて10年以上の年月が経過しています。
幸い、現在も、現役の量産技術として活用されています。(2016年時点)
こうした生産技術開発の中で、自動車部品に求められる仕様の変化を感じました。
軽量化競争の中、新たに固有振動現象への対応も求められる車種も出てきたのです。
従来製法で開発した製品を基準として軽量化が5%、10%と進んでいく中で、要求が強まってきました。
部品の軽量化が進んでいない時は、そもそも問題にはならなかった部品の剛性問題です。
軽量化、つまり部品の構成部材が薄肉になると、部品は変形しやすくなります。
その結果、製品全体の剛性が低下する問題に直面します。
製品の剛性が乗り心地や走行音に関係するとのことでした。
製品の固有振動値も設定数値以上との仕様が強調される状況に変わってきたのです。
エンジンやタイヤの静粛性が高まってきたことも背景にはありました。
単なる軽量化のみではなく、「剛性も維持できる薄肉化」。
こうした、律背反の技術課題に直面する場面が増えてきたことを思い出します。
軽量化を優先させて薄肉にすると、剛性が下がり固有振動値が下がる。
一方、剛性を優先させて厚肉設計すれば、
剛性が上がり固有振動値も上がって強度テストにもパスしやすくなるが、軽量化目標は達成できない。
軽量化と剛性を両立させるのに、日々、うんうん唸っていました。
その中で、さらに、意匠性を高める特殊塗装へのニーズも高まってきました。
当時扱っていた部品は、もともと意匠性も求められていた部品です。
見た目も重視、ではあったものの、
それまでは、よほどの特殊な用途でもない限り、特別な塗装を求められることはありませんでした。
カスタマイズカー向け部品などです。
それが、標準仕様の車種でも、意匠性を高めるために特殊塗料が求められるように変わってきたのです。
塗装技術を担当する技術部隊が、技術開発を進めました。
軽量化ニーズ ⇒ 軽量化+高剛性ニーズ ⇒ 加えて特殊塗装。
お客様が求めるニーズが変化してきました。
自動車を購入する最終顧客の嗜好が多様化すれば当然のことでした。
2.機能競争では圧倒的な差別化技術がなければ儲かりにくい
さて、自動車部品では、材料費+加工費がベーシックな見積もりです。 だから、自動車メーカーは、使った材料費分は支払ってくれます。 この見積もりルールで軽量化を進めるとどうなるか・・・。 自動車部品を軽量化した分だけ材料費は低減され、単価は下がる。 そして、軽量化の加工費が従来対比で上昇すると、利益率が下がってしまう。 軽量化のために、加工技術を高度化する技術開発は、しばしばなされます。 この場合、技術開発に要したコストを回収するのが難しくなるのです。 なんとも、報われない流れになる懸念がありました。 そこで、軽量化分のコスト削減分は折半する相談を、顧客へ持ちかけたこともあります。 こうして、軽量化の技術料をいただく相談をしたのです。 極めて革新的な技術であるならば、顧客もプレミアムを出しやすかったかもしれません。 部品重量が半分以下になるくらいの圧倒的な成果ならです。 一方、従来対比で5%、10%減程度の軽量化の場合はどうでしょうか。 技術的な障壁は、高いかもしれません。 が、顧客にとって、その成果のインパクト度合いが、必ずしも大きいとは限りません。 したがって、技術料を価格へ反映したいものの、そう簡単にできることではないでしょう。 圧倒的な軽量化なら、技術料による価格アップも受け入れられ易かったかもしれません。 ”圧倒的な”差別化技術なら、競合が絶対に達成できない成果を提供できるからです。 競合も頑張ります。
客観的に判断しやすい分だけ、ますます競争も激化していくのです。
その結果、ますます、技術料を価格へ反映させるのは難しい状況に陥ります。
客観性の高い仕様では、明からに差別化された魅力がない限り、技術料を価格へ反映させるのは難しい。
供給者側は頑張っても、その頑張りを簡単に価格へは反映できないという、当然のことを実感しました。
「圧倒的な」差別化技術により、初めて、値付けの主導権を握れるということです。
競合も頑張ります。
客観的に判断しやすい分だけ、ますます競争も激化していくのです。
その結果、ますます、技術料を価格へ反映させるのは難しい状況に陥ります。
客観性の高い仕様では、明からに差別化された魅力がない限り、技術料を価格へ反映させるのは難しい。
供給者側は頑張っても、その頑張りを簡単に価格へは反映できないという、当然のことを実感しました。
「圧倒的な」差別化技術により、初めて、値付けの主導権を握れるということです。
