戦略的工場経営ブログ戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント6
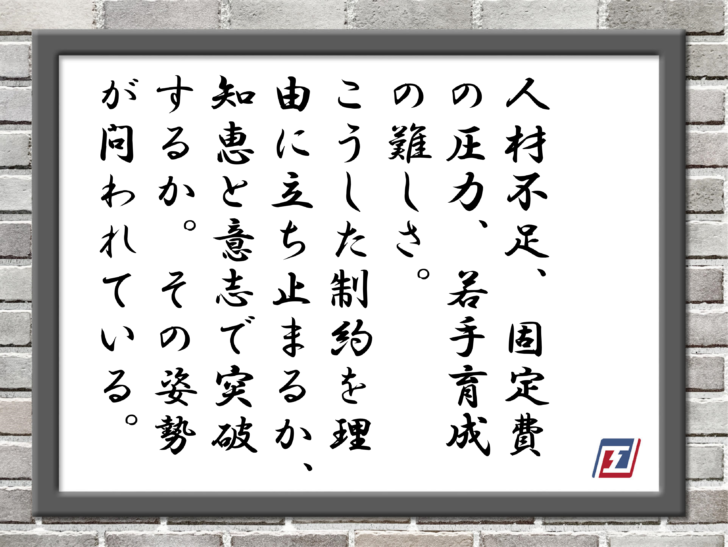
先月のブログ「戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント5」のテーマは、「将来を見据え、率先して行動するリーダーシップ」でした。
1号艦「大和」の船体(船殻)建造総工数を、2号艦「武蔵」の半分にできた背景には、新たな要素技術の導入だけではなく、新たな管理技術やリーダーシップの下支えもあったのです。
トップは常に将来を見据えます。将来を見据えるとは、新たな土台をつくることに他なりません。
精神論や根性論ではなく、科学的視点で改革を進めようとする伍堂卓雄海軍造兵中将のような海軍幹部が、当時の日本にいたことは、製造業にとって、幸運でした。
https://hajime-i.com/2025/08/15/blog421/
戦艦大和の建造でリーダーシップを発揮していた西島技術大佐の方針ははっきりしていました。生産性を高めることです。超弩級戦艦を完成させなければなりません。納期の予算も制限があるのです。
西島技術大佐は、能率曲線による工数管理、金物統制や材料統制に加えて、まだまだ多くのの取り組みに挑戦しました。今回のブログでは、西島技術大佐のさらなる効率アップの実績を取り上げます。
出典は全て藤間孝則著「戦艦大和誕生」です。
1.人員数を増やせなかった状況は今の中小製造現場と同じ
戦艦大和は昭和12年(1937年)11月に起工しました。その翌月12月、西島技術大佐は、船殻部門の責任者に就任しました。
船殻とは、戦艦で海面に浮かぶ本体部分のこと。つまり西島氏は、巨大な船体部分を建造する責任を担ったのです。そして、ここで船体建造総工数を2号艦「武蔵」の半分にするという画期的な成果を出しました。
当時、呉工廠の能力だけで超弩級戦艦を建造するのは不可能と考えられていました。前任者は従来通り、近隣の造船所に外注する方向で考えていました。
しかし、西島氏は、その方針を覆し、「呉工廠内で全て加工する」と決断します。理由は明確で、最高機密保持のためです。外部に図面を出せば情報漏洩のリスクが高まります。
そこで、西島氏は人員を増やすのではなく、身元の確かな工員を厳選し、必要最小限の人数で建造をやり切る方針を打ち立てました。少数精鋭で挑んだのです。
この状況は、今の中小製造業と重なります。
ベテランが退職しても代わりが見つからず、採用市場では若手人材も不足。人を増やしたいが応募者が集まらない。一方で、固定費が重くのしかかるので、安易に人を増やせない──多くの経営者が同じ悩みを抱えています。
言うなれば「限られた人数で成果を上げるしかない」環境に立たされているのです。90年前に西島技術大佐がやり切ったように、制約を逆手にとって知恵を絞るしか道はありません。
2.生産性を高めた新たな挑戦
大和建造で導入された新しい要素技術の一つが「早期艤装」です。
艤装とは、砲塔や艦橋をはじめ、エンジン・電気設備・通信機器を船体に取り付ける作業のこと。当時は船体を進水させた後に艤装を行うのが普通でした。
しかし、西島技術大佐は進水前に艤装をスタートさせる、船殻工事と艤装工事を並行させた方式に挑戦したのです。艤装工事を早期に始めることで、リードタイムを短縮し、工数を低減しようとしました。
「早期艤装」を工程管理に当てはめれば、「工程の前倒し」や「同時進行」の発想です。例えば、金型製作において、粗加工と仕上げ工程を一部並行させる、あるいは試作品と量産準備を重ねる、といったやり方に通じます。
ただし「早期艤装」の実現は容易ではありません。船殻工事と艤装工事を組み合わせた、綿密な計画を立てなければなりません。
必要な部品の納入や工程間の調整を徹底しなければ、全体が混乱し逆効果になります。全体の進捗を把握する仕組みも必要です。
だからこそ、トップの強力なリーダーシップが不可欠でした。遅れが出れば即座に挽回策を講じる──その統率力が現場を動かしたのです。
今日の中小製造業も「短納期要求」に直面しています。人員不足による計画遅延の挽回を後工程に押し付ければ、納期遅れや追加残業が発生します。
早期艤装の考え方は、単なる造船技術ではなく「トップの覚悟で並行処理をやり切る」発想です。西島氏は、今の経営者に、リーダーシップの有無を問うているのではないでしょうか。
3.設備レイアウト変更も実践した西島技術大佐
西島技術大佐は、工場内の設備レイアウト変更にも踏み切りました。
長年動かされずに置かれた古い機械、空きスペースに場当たり的に設置された新設備──こうした配置を一新し、モノの流れを考慮した動線へと組み直したのです。
さらに、移設による生産停止を最小限にするため「外段取り」を徹底。基礎工事や配線を事前に済ませ、1台ずつ短期間で移設を終える工夫をしました。現在では当たり前のようにやられている「外段取り」ですが、当時の海軍では初めてです。
それまで、設備移動時の生産停止ロスが心配で、誰も設備再配置をやっていません。西島氏が、初めて、やってのけました。
これは現代の工場にも当てはまります。気づけば増設した設備が点在し、現場の動線は迷路のよう。創業者が立てた工場に、追加、追加で工場を拡張してきた現場はこうなっています。
作業者は無駄な移動で疲弊し、生産性は下がる一方です。西島技術大佐の取り組みは「少数精鋭で成果を上げるために、モノの流れを整える」という基本を教えてくれます。
さらに大事なのは、トップ自らが現場を主導した点です。現代の中小製造業でも「人手不足だから仕方ない」「若手が育たない」と嘆くだけでは現場は変わりません。
経営者が方針を明確に示し、なぜ改善が必要かを語ることで、現場はその意志を感じ取り、改善マインドが芽生えます。これは今も昔も変わらぬ真理です。
4.日本が造船世界一となる基盤をつくった西島技術大佐
西島技術大佐は、単なる技術導入にとどまらず、要素を有機的に連動させました。彼の言葉を引用します。
「早期艤装を完全に成功するためには、軍艦では船殻工事の区画毎の完成とか、実物大模型の製作とか、出図の促進とか、制式の制定とか、材料の統制とか、工数の統制とか、他部関係工事の推進等巧妙に実施せねば大きな成果をあげ得ない。」
この言葉が示すように、仕組みは単体で機能しても成果は出ません。全体が巧みに組み合わさり、有機的に連動して初めて効果を発揮します。
仕組みをつくっても「魂」を込めなければ空回りです。経営の現場に置き換えれば、工程間連携や製販一体の仕組みを本当に機能させるには、リーダーシップ以外の道はない、ということです。
さらに、西島氏はこうも語っています。
「従来、日本の造船界では、進水までは船殻工事のひとり舞台であって、わずかに進水前工事がという舞台でなければできない仕事だけしていたが、これは大きくあやまっていることを痛切に感じ、これによって建造期間も短縮され、能率的にもすなわち経済的にも有利に建造できるだけでなく、造船能力も増大できることを発見した。」
制約条件の中で、現状を直視し、望ましい姿を描き、改革をやり抜く。
大和建造で実現された数々の挑戦は、戦後の商船建造に受け継がれ、日本を「造船世界一」へ導いたのです。技術立国・日本の基盤を築いたのは、こうした先輩エンジニアの努力に他なりません。
現代の中小製造業も同じです。人材不足、固定費の圧力、若手育成の難しさ──制約は数多く存在します。しかし、それらを理由に立ち止まるのか、知恵と意志で突破するのかが問われています。
人時生産性を高め、未来に生き残るためには、今まさに、「経営者がどんなリーダーシップを発揮できるか」が試されているのです。貴社は、挑戦していますか?
