戦略的工場経営ブログ戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント5
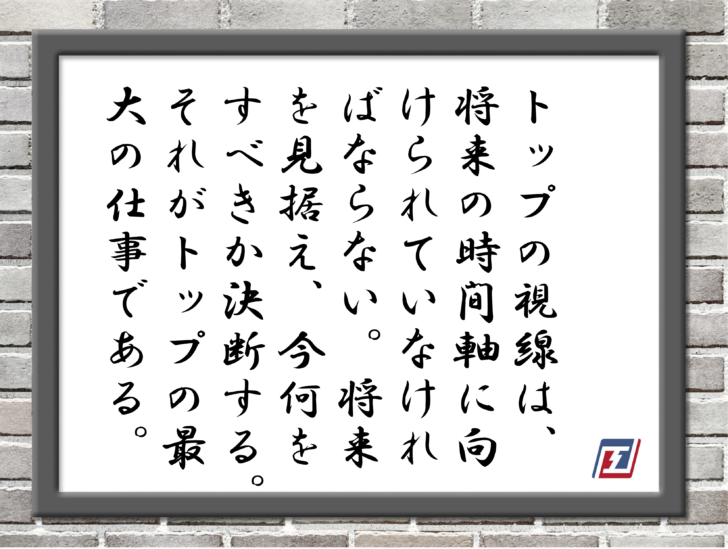
先月のブログ「戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント4」のテーマは、「標準化を継続させる取組み」でした。
1号艦「大和」の船体(船殻)建造総工数を、2号艦「武蔵」の半分にできた背景には、新たな要素技術の導入だけではなく、新たな管理技術の下支えもあったのです。
ルールをつくるだけでは、標準化を継続できません。ルールを守らせること、ルールを更新しつづけること。これらも必要です。
巨大戦艦建造プロジェクトを率いたトップ層のひとり、西島亮二海軍技術大佐はそのことを知っていました。強力なリーダーシップを発揮し、標準化を定着させていったのです。
https://hajime-i.com/2025/07/15/blog420/
リーダーシップを発揮したのは、西島技術大佐だけではありません。呉工廠では西島氏が奮闘する以前から、多くの先輩方が合理化や効率化に挑戦していました。
「大和」建造期(1937年以降)から遡ること10年ほど前、呉工廠の工廠長を担った伍堂卓雄海軍造兵中将は、そうしたひとりです。今回のブログでは、伍堂卓雄海軍造兵中将の実績を取り上げます。
出典は全て藤間孝則著「戦艦大和誕生」です。
●強力なリーダーシップの成果
仕組みは、つくっただけで成果につながりません。新しいルールが日常の仕事に組み込まれ、「それが当たり前」になって、ようやく継続的に守られ機能するようになります。
重要なのは、ルールを作るだけでなく、守らせること、そして変化に合わせて更新し続けることです。これらの指導を怠れば、仕組みは形骸化します。
モノづくりは、今や、高度化・複雑化しました。個の力だけで、人時生産性を高めることはできません。必要なのはチーム力です。そしてそのチーム力を決めるのは、メンバーの能力ではなく、トップの姿勢しかありません。全てトップ次第です。
トップが決断し、率先して行動し、困難を乗り越えた度合が、成果の多寡を左右します。うまくいかない原因を現場や構成メンバーに帰結させるのは論外です。
そんな現場で、トップダウンが機能するわけはありません。自主性の現れである「現場からのボトムアップ」は望むべくもないのです。トップが自ら行動することで、トップダウンが機能し、その結果、ボトムアップが引き出されます。
西島技術大佐のリーダーシップは、その好例です。西島氏の仕事ぶりには、使命感と執念がありました。「日本のためにはこれしかない」という信念のもと、金物や材料の標準化に挑んだのです。
標準項目や全体構成の策定、新しい標準を現場全員に浸透させる指導、さらに最新情報を反映する地道な更新作業…。そして、現場は西島氏についていきました。
強力なリーダーシップによるトップダウンとボトムアップがあったのです。その徹底ぶりが、西島式管理方式というシステムに結実しました。
強力なリーダーシップと上司を信じた部下との信頼関係の結果と言えます。そして、そのすごさを証明するエピソードが次のように紹介されています。
「昭和40年代はじめごろ、日本を代表する呉造船所に初めて総合的なコンピューターシステムの導入が図られた。このとき、プログラム担当者は大いに驚かされた。40年近くも前に考案された西島式材料管理方式が、基本的な手なおしをほとんどすることなくコンピューターにインプットできて、切り替えられたからだ。」
仕組みの完成形は自動化です。具体的には、DX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組みます。
ここで真に難しいのは、DXそのものよりも、導入前の事前準備です。システム全体が体系化されていなければ、コード化できません。あいまいな設計では、プログラムが複雑化し、むしろ混乱を招きます。
西島技術大佐の管理方式は、まるで40年後のDX時代を予見していたかのように整然と標準化されていたのです。トップが全責任を負う覚悟とリーダーシップの賜物でした。
強力なリーダーシップは本気の仕組みづくりの原動力です。
●伍堂卓雄砲熕部長の取組み
呉工廠砲熕部長だった伍堂卓雄海軍造兵中将は、戦艦大和建造の15年ほど前に、ある標準化を導入しました。それが、今の製造現場では普通に使われているリミットゲージ(穴ゲージ)です。
砲熕部は大砲の製造を担っていました。砲弾が通る穴の精度は命中率を左右します。内径には上限と下限があり、加工は公差内でやられなければなければなりません。
熟練していない作業者が恐れるのは「削りすぎ」です。その結果、少し削ってはメジャーで内径を測定し…を繰り返します。これでは作業効率が落ちてしまいます。
リミットゲージの導入により、作業者はゲージを当てるだけで、合否を判定できるようになりました。測定の手間が減り、読み間違いも防げます。砲熕部での成果は次です。
工費:約30%削減
作業時間:48%短縮
納期:234日 → 53日に短縮
製品精度:大幅向上
リミットゲージの導入という作業の標準化により、大きな成果が得られました。そして、これらは、同時に進めた組織改革との相乗効果の結果でもあったのです。呉工廠では、次の組織改革も並行して進めていました。
・計画部の設置: 工廠全体の生産計画を一括管理
・機能別設計体制: 設計・製図・製作・検査を分業し、精度を統一
それまで、各工場(砲熕、機関、船殻など)が独自に工程を組み、全体の進捗は人間関係や経験で調整していたのです。
さらに、1人の設計者が大砲の全工程(設計・製図・製作・検査)を抱え、担当ごとにやり方や精度がバラバラでした。そうした属人的な仕事をシステム化したのです。
この時点で伍堂海軍造兵中将はまだ一職場の部門長でした。しかし、後に工廠長となり、属人的運営を日程計画と標準化を軸にした工場システムへと変革していきます。
その背景には、標準化の価値を深く理解したリーダーの信念があったのです。
伍堂氏の仕事ぶりは、「チームの成果は構成メンバーの能力ではなく、トップの姿勢次第である」ことを教えてくれます。
●大和ミュージアムの展示品を見ながら考えたこと
訪問した大和ミュージアムには、砲熕部で使われたリミットゲージや、組織改革後の機能別組織表が展示されていました。寸法違いのゲージがシリーズで並び、黄ばんだ用紙には呉工廠全体の組織構成が記されていたのです。
今では当たり前の道具や組織形態ですが、90年前の日本で先人たちが、悪戦苦闘しながらこれを使っていた姿を想像すると、胸が熱くなります。
西島技術大佐は、伍堂海軍造兵中将ら先輩技術者が築いた土台の上で、大和の画期的な建造方法を実現しました。その精神は、現代の中小製造業の現場にも息づいています。土台が引き継がれ、さらにその上に新たな土台が築かれるのです。
トップは常に将来を見据えます。将来を見据えるとは、次世代の新たな土台をつくることに他なりません。トップが現場と一緒に足元の仕事をやっているだけではチームの豊かな成長はないのです。
モノづくりの高度化が進む今こそ、トップは将来を見据え、「将来のために、今やるべきこと」を、チームで実践しなければなりません。
●伍堂海軍造兵中将が改革を決断したきっかけ
伍堂氏がリミットゲージ・システムを導入した背景には、長い欧米駐在で得た知見がありました。海外の産業合理化や能率向上策を目の当たりにし、日本との生産性の差を肌で感じていたのです。伍堂氏はこう語っていました。
「労働者ひとり当たりの生産高を比較して見ましたのに、日本の労働者の1に対し英国労働者は5.3、米国労働者は7.0の如き比較数字を得、(中略)彼我の間に如何程体力の相違ありとしまするも、吾々2人で欧米人ひとりにかなわぬ訳はないので、之は決して体力のみに依る相違ではない。」
伍堂氏は日本の労働者の生産性が欧米の5分の1,7分の1であることを危惧していたのです。体格差以上の差異があると解釈した、この発言は的を射ています。
原因は現場の能力ではなく、やり方そのものにあると喝破していたのです。日本が生き残るには、将来へ向けて、労働者の生産性を上げなければならないと見抜いていました。
外を知らなければ、こうした的確な解釈はできません。トップ層が内弁慶ではダメです。我が社と比べる対象を積極的に外へ探しにいきます。
精神論や根性論ではなく、科学的視点で改革を進めようとする海軍幹部が、当時の日本にいたことは、製造業にとって、幸運でした。こうして、日本の現場における標準化の第一歩が踏み出されたのです。
トップの視線は、将来に向けられていなければなりません。将来を見据え、今、何をすべきかを決断し、率先して行動しながら、困難を乗り越えていく。これがトップの最大の仕事です。これは、90年前も、そして現代の中小製造業においても変わらない真理です。
モノづくりの本質はチーム力を活かすことにあり、そのチームのベクトルを揃えるために、経営者は、将来に向けて、今、何をやらなければならないかをメンバーに伝えます。
日本が生き残るには、将来へ向けて、労働者の生産性を上げなければならないと見抜いていた伍堂海軍造兵中将の姿勢は90年前であっても、学ぶことが多いです。
貴社では、将来を見据え、今、何をすべきかを決断し、率先して行動しながら、困難を乗り越えていますか?
