戦略的工場経営ブログ戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント10
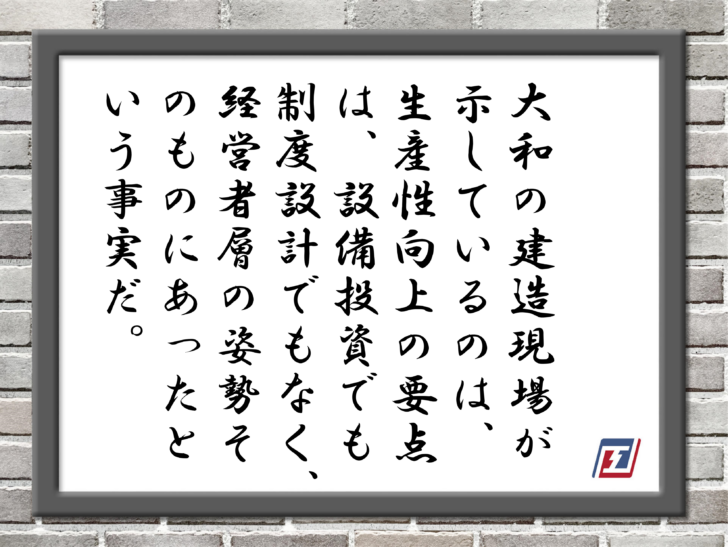
先回の「戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント9」のテーマは、「要素技術と管理技術」、そして「トップ層のリーダーシップ」でした。
この三つが揃って、大和建造時の外部環境変化に対応できていたことが確認できます。これは、戦時下の巨大プロジェクトだけでなく、いま中小製造企業が直面している現実にも、そのまま当てはまる考え方です。
https://hajime-i.com/2025/12/15/blog425/
これまでの出典は、すべて前間孝則氏の『戦艦大和誕生』でした。今回は別の視点として、御田重宝氏の『戦艦大和の建造』を参照させていただきます。
本書は『戦艦大和誕生』より10年ほど前に出版されたものですが、会話文が多く差し込まれ、作業者一人ひとりの仕事ぶりや息づかいが伝わってくる感じがしました。
今回の「人時生産性向上へのヒント10」では、当時の現場作業者の姿を思い浮かべながら、現場の職人技を引き出した、船体建造をけん引した西島亮二技術大佐をはじめとした経営層のリーダーシップとは何だったのかを改めて考えます。
この問いは、戦艦大和という特殊な事例に限らず、人時生産性や生産管理に悩む中小製造業の経営者にとっても、避けて通れないテーマではないでしょうか?
出典のほとんどは、御田重宝氏の『戦艦大和の建造』です。会話部分を多く引用させていただきました。
1.旧呉海軍工廠の大型旋盤「15299機」
大和ミュージアムの敷地で、思わず足を止めて見上げてしまう展示物があります。旧呉海軍工廠の大型旋盤「15299機」です。1938年にドイツから導入され、戦艦大和の主砲などの加工に用いられました。
本体は長さ約20メートル、幅・高さはいずれも約5メートル、重量は約220トンともいわれています。鋼材を取り付ける面盤の直径は3.2メートルに及びます(出典:きしろグループの金属&樹脂加工Naviサイト)。
ミュージアム本館とは別の場所で展示されているこの巨大な旋盤を目の前にすると、数字で知っていた規模感とはまったく違う迫力があります。設備というより建造物に近い存在です。90年前、これを操作していた現場があったことに、静かな感動がありました。
この旋盤で削り出された46センチ主砲は、口径46センチ、長さ約20.7メートル、重量は約160トンにもなります。
その巨大な鋼塊を、刃物の位置や切り込み量を読み取りながら、切り粉と熱気に包まれた現場で加工していった当時の作業者の姿が、自然と目に浮かびました。
寸法誤差は許されず、一本の主砲に何日も向き合う仕事です。
今から90年も前、まさにこの旋盤を操りながら、時間と神経を削り、国家の命運を背負う加工に挑んでいた現場が、ここにあったのです。
2.46センチ砲の焼きばめ
戦艦大和の46センチ砲は、当時として世界最大級の主砲でした。弾丸は長さ約2メートル、重量は約1トン460キログラムにもなり、これを押し出すために約330キログラムの火薬が使われます。
その爆発力によって、弾丸は約4万800メートル先まで到達します。東京駅から横浜駅を少し越える距離、大阪駅から京都駅の手前まで届く距離です。
このとき砲身内部には約3,300気圧もの圧力がかかるといわれています。この過酷な条件に耐えるため、大和の主砲は多層構造で設計されました。
内側から1A、2A、3A・・・と層を重ね、外側の層が内側を締め付ける構造です。その要となった要素技術が「焼きばめ」という加工方法でした。
焼きばめとは、金属の熱膨張と冷却収縮を利用し部材同士を精密に結合させる技術です。
例えば、仕上がった3Aの外側に4Aを加熱してはめ込み、冷却して一体化させます。世界一の主砲を成立させた背景には、この原理を正確に現場で実現する技術力がありました。
計算上は成立していても、実際に寸分違わず組み上がるかどうかは別問題です。理屈・理論を「使える技術」として扱える現場力が無ければなりません。コア技術の使いこなしです。コア技術の使いこなし、これは人時生産性を高める最大の論点と言えるでしょう。
3.焼きばめ作業の精度を支える職人芸
仕上がった3A(内側)と4A(外側)を焼きばめするにあたり、まずは、外側となる4Aの仕上げ加工が行われます。4Aでは、旋盤で外径を、内側は中ぐり加工機で内径を、それぞれ定められた寸法に仕上げていきます。
この仕上げ工程だけで、約20日間を要したとされています。完成した3Aと4Aは、その後、熱処理工場へと送られました。
砲身の焼きばめが行われたのは、地下に掘られた深いピットです。長さ20メートルにも及ぶ砲身を横にして加熱すれば、自重でわずかにたわみ、狙った精度が出ません。
そこで、砲口を下に、砲尾を上にした立てた姿勢のまま処理する方法が採られました。変形を避けるための現場の知恵です。
焼きばめ作業の様子が次のように記述されています。
ピットで、4Aは200度程度に加熱される。砲口を下に、砲尾を上にして、立てたままの処理である。数時間の加熱で、4Aは均等に膨張する。つまり、3Aを入れる内径が大きくなる。それらは計算で正確にはじき出される。
「よし。行こう」
組長の声で、ガン・ワイヤを巻いた3Aがクレーンに吊られ、ゆっくりと降りてゆく。
「ちょい右」
「ちょい前、ゆっくり」
巧妙なクレーン操作で、3Aが4Aの真上に導かれる。
「よし、降ろせ。落ち着いてやれ」
数人の工員は、ピットの中に入って、3Aを支え、正確に4Aの中に入るように調子をとる。
砲身の自重で、3Aは、吸い込まれるように4Aの中に入ってゆく。
加工技術がすぐれているので、二つの砲身は、ぴたりと重なり合う。カーブをもって太くなっている砲尾部分も、寸分の誤差もなく密着する。
「よし、冷却」
ピットの中で、周囲から冷水が一斉に放出される。一度膨張した4Aは、冷却水によって収縮し、3Aをムクの鉄塊のように抱き込む。
今から90年前の現場です。世界一の主砲を実現できた背景には、計算式だけでは語れない現場の技能がありました。
ベテラン作業者が持つ感覚や段取り力が、理論と理論のわずかな隙間を埋め、最終的な擦り合わせ精度を支えていたのです。これは、時代が変わっても変わりません。
こうした技能が偶然に生まれたわけではない点も見逃せません。呉工廠には養成機関があり、当時の尋常小学校卒業程度の見習工であっても、基礎知識から体系的に学ぶ機会が与えられていました。
経験と勘だけに頼るのではなく、知識に裏付けられた技能を育てる仕組みがあったからこそ、世界水準の仕事が安定して再現できたのです。
4.甲鉄(装甲板)を設置する職人技
戦艦は文字どおり「戦うための船」です。攻撃力と同時に、防御力もなければ勝てません。
大和の船体設計では、構造強度の確保に加え、被弾に耐えるための防御構造が徹底的に検討されました。その象徴が、船体の上面および側面に設置された甲鉄(装甲板)です。
船体上部には、甲鉄を組み合わせた厚さ約200ミリの装甲が取り付けられました。これらは製鋼部で鍛錬された甲鉄を、甲板工場で寸法どおりに組み上げたものです。
特筆すべきは、組立時に鋲を用いなかった点です。代わりに用いられたのが、クサビを打ち込んで結合する方法でした。強度実験の結果から導き出された、海軍独特の工法です。
そして、大和の設計思想は「ただ頑丈にする」ことに留まりません。構造強度に影響しない範囲で、鉄板には意図的に穴が設けられていました。
巨大戦艦でありながら、100グラム単位の軽量化にまで配慮していたのです。軽量化も大和建造での重要な課題でした。
こうした「穴あけ標準化」を進めたのが、西島亮二技術大佐でした。防御と軽量化という相反する要件を、設計と現場技術の両面で成立させていたことが分かります。
さて、甲鉄をクサビで固定するためには、完全に一致する「でっぱり」と「へこみ」を作り込む仕上げ作業が不可欠でした。
ほんのわずかな狂いでも、クサビは利かず、装甲としての性能は発揮できません。ここで求められたのが、長年の経験に裏打ちされた名人芸でした。
製造部長の庭田尚三技術少将が、仕上げ現場を視察したときの出来事が記されています。
現場を巡回していた庭田技術少将は、厚さ約100ミリの甲板の切れ端に、桜の花の模様を彫っている一人の中年工員に目を留めました。
その工員は、作業にひと区切りつき、手持ち無沙汰を紛らわせるように、甲板に桜を彫っていたようです。
本来の仕事ではありません。しかし、その表情は真剣そのもので、目の細かいやすりを使い、丹念に仕上げていました。
庭田技術少将は、工員のすぐ横まで歩み寄り、何も言わずに、その手元を見つめ続けます。
「暇つぶし」に没頭していた工員は、やり終えた後、ほっと一息つき、横にいた同僚・・・と勘違いし、少将が横にいたとも知らず、庭田技術少将に出来上がった作品を見せました。
そのとき、ふと視界に入った帽子の徽章に気づき、腰を抜かさんばかりに驚きます。自分の横に立っていたのは、造船部長の少将だったからです。
仕事ではなく、暇つぶしを見られてしまった、その驚きは、想像に難くありません。その後のやり取りが、次のように描かれています。
一工員が、造船部長の顔を見ることは、まずない。しかし、帽子のマークは、まぎれもなく少将であり、同伴している者は、いずれも技師、将校の服装である。
「何かね」
庭田が尋ねた。返事がない。できないのである。前の作業台に、ムクの桜の花型に細工された棒がころがっているのを見て、庭田が言った。
「入れてみなさい」
庭田自身、興味の方が先に立っていた。工員は、ふるえながら、桜の花型の細工物を油缶の中でひたし、同じ桜の花型を彫りぬいた甲板の上に置いた。
油がついているので、細工物は、すっと、引力に引き込まれて没した。
(中略)
長さ100ミリの鉄の棒に桜の花型を彫り、別の甲板に、同じ型のものを彫りぬく。二つを一つにすると、すっぽりとはまって、別々に造ったという跡形も残さない技術。「ほ、ほ、ほう」
庭田は工員の肩をポンと叩くと、ニヤリと笑って歩き去った。
現場責任者が、大声で工員をどなっているのを後に聞きながら、庭田はこの技術が「1号艦」を完璧なものに育て上げると、強い自信を持った。
当時の呉工廠では、明治23年(1890年)の工廠設立以来、受け継がれ、育てられ、鍛えられてきた技術が、まさに頂点に達していたと説明されています。
仕上げ名人、型取り名人、ひずみ取り名人、鋲打ち名人──こうした名人が、あらゆる部門に存在していました。
重要なのは、こうした名人芸が自然発生的に生まれたものではない点です。「お国のためにがんばる」という動機付けに加え、技能を認め、現場を見に行き、黙って評価する上司の存在がありました。
経営者層が、現場をどう見ているか、その姿勢そのものが、技術を受け継ぎ、育て、鍛え続ける原動力になっていたのです。
5.甲鉄(装甲板)を設置する知恵
甲鉄(装甲板)は、船体の側面にも取り付けられました。側面の甲鉄は厚さ約410ミリ、高さ約6メートル、幅約3.6メートル、重量は約68トンにも及ぶ巨大な部材です。
船体側面が垂直であれば、クレーンで吊り下げ、そのまま密着させられます。しかし、大和の船体側面は場所によって外側に約20度も傾斜しており、単純な吊り下げでは対応できませんでした。
このため、クレーンで吊った甲鉄の下側を盤木で押し付けながら、船体に密着させ、ネジで締結する必要がありました。海軍工廠の能力をもってしても、この作業は容易ではなく、現場では「どうしたものか」と頭を悩ませていたといいます。
何か良い工夫はないかと関係者の間で話題になりました。そして、この問題をいとも簡単に解決した工員がいたのです。見習工出身で現図場にいた岡田善吉氏です。
そのいきさつが次のように記述されています。
「そんなこと簡単じゃないか」
現図場で、しゃがみ込んだままタバコを吸っていた岡田は、タバコをもみ消すと耳に挟んで言った。
「6トンもあるものを、20度に傾斜させ、舷側に取り付けるんだぞ」
「じゃけえ、最初から20度に甲板を傾けて、クレーンに吊ればええじゃないか」
「最初から20度傾ける?」
岡田は、床に、筆で簡単な図面を描いて見せた。
「あっ」
だれもが声を立てた。甲板の重心を、20度に傾けるように吊るジグの考案である。
「うちの工廠で、50トンや60トンの甲板を吊るジグを造るなあ、簡単じゃと思うがの」
それだけ言うと、再び現図の作業にかかった。
岡田の考案したジグは、その日のうちに造られ、試してみると非常に具合がよかった。そして岡田の考案は、その日のうちに砂川工廠長の耳に入った。
「学問は、しておくもんだね」
砂川は上機嫌で、工廠長表彰の手続きをとらせながら、庭田に言った。
「うちの工員の素質は優秀ですからな」
庭田は自分のことのように得意がった。
工廠長表彰という、考えてもみなかった栄誉の知らせを聞いたとき、
「えらい人は、高等数学しか覚えちょらんけえ、分数を忘れちょる。じゃけえ、わしは学問をせんのよ」
岡田は照れながら、そして顔をくちゃくちゃにしながら、なお、へらず口をたたいていた。生涯一工員のままという、彼なりのプライドの表明であった。
「現場のことは現場が一番知っている」。よく耳にする言葉ですが、現場の知恵は、放っておいて、自然に出てくるものではありません。
知恵を働かせたい、工夫を提案したいと思える環境があって、はじめて表に出てきます。黙っていてもよいの立場にあった岡田氏が、あえて自ら口を開いたのです。
その背景には、砂川工廠長や庭田技術少将の姿勢があったと推測できます。経営者層の二人は、現場から上がってきた発想を面白がり、素直に喜び、きちんと評価しました。こうした上司の言動は現場に伝わるものです。ある雰囲気が醸成されるのはないでしょうか?
評価された岡田氏自身も、顔をくちゃくちゃにしながら嬉しさを隠しきれなかったと描かれています。普段は顔を合わせることも少ない上司であっても、「見てくれている」「分かってくれている」と感じられれば、人はもう一歩踏み出します。
現場の知恵を引き出すかどうかは、仕組み以前に、経営者層のリーダーシップにかかっています。現場が考え、提案し、工夫する。その循環を生み出せるかどうかが、組織の力を決めるのです。
6.現場の職人技を引き出す経営層のリーダーシップ
ここまで見てきた大和の建造現場では、特別な英雄が奇跡を起こしたわけではありません。巨大旋盤、焼きばめ、甲鉄の据え付け、いずれも高度な技術ですが、それを「使える力」に変えていたのは、現場に蓄積された技能と知恵でした。
そして、その力を最大限に引き出したのが、経営層のリーダーシップです。
注目すべきは、経営層が細かな指示で現場を動かしていない点です。彼らがやっていたのは、現場を見に行き、仕事ぶりを感じ取り、価値ある技術や発想に静かに反応することでした。
桜の花を彫った職人の技に目を留め、岡田氏の発想を面白がり、即座に評価する。その一つひとつの態度が、「この現場なら考えたい」「工夫したい」という空気をつくっていたのです。
人時生産性向上とは、作業を急がせることではありません。一人ひとりが持つ判断力や技能を、必要な場面で自然に発揮できる状態をつくることです。
その前提になるのが、経営者自身の現場への向き合い方です。
さて、貴社の工場ではどうでしょうか。
現場は「見られている」と感じているでしょうか。心から喜んで知恵を出しているでしょうか。評価は、制度や紙の上だけでなく、経営者自身の言葉と態度で示されているでしょうか。
現場の職人技は、放っておいて育つものではありません。しかし、正しく見て、正しく受け止める経営層がいれば、現場は必ず応えます。
大和の建造現場が示しているのは、人時生産性向上の出発点は、設備投資でも制度設計ではなく、経営者層の姿勢そのものにあったという事実です。そして、その姿勢は、今日でも問われているのです。
