戦略的工場経営ブログ戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント2
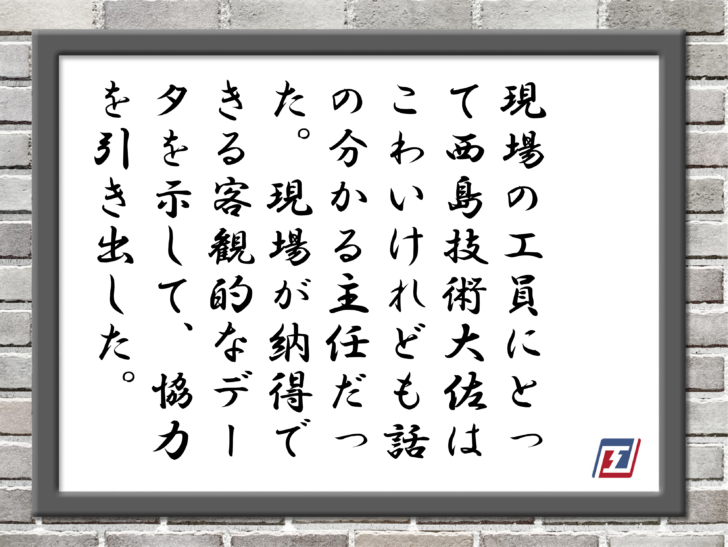
先月のブログ「戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント1」では、1号艦「大和」の船体(船殻)建造に要した総工数は2号艦「武蔵」の半分だったことを取り上げました。出典は前間孝則氏の著書「戦艦大和誕生」です。
https://hajime-i.com/2025/04/15/blog417/
引き続き、2です。西島技術大佐をはじめ多くのエンジニアによって発揮された強いリーダーシップの様子から「モノづくりの本質」を考えたいのです。
弊社は、人時生産性を高める観点で、中小製造企業経営者の支援をしています。「モノづくりの本質」から中小製造企業で人時生産性を高める要点が見えてくるはずです。
1.要素技術と管理技術をセットで実践した先見性
巨大戦艦建造プロジェクトを率いたトップ層のひとりが西島亮二海軍技術大佐です。「ブロック建造法」と「先行艤装(ぎそう)」の採用、「リベット(鋲接)工法」から「電気溶接法」への移行など、革新的な建造法を導入しました。
今では当たり前にやられている技術です。それを90年前の日本で導入しました。さらに注目したいのは、近代的な生産管理の手法を実践したことです。革新的な建造法も、それを支える生産管理がなければ成果を出すに至りません。
製造業で、持続的競争優位を構築する源泉はコア技術です。そして、コア技術は、要素技術と管理技術の2つがセットになります。一方だけでは、成果は限定的です。
新たな「要素技術と管理技術」に挑戦したトップ層のリーダーシップがあったから、「1号艦「大和」の船体(船殻)建造に要した総工数は2号艦「武蔵」の半分だった」という革新的な成果が得られました。
西島技術大佐は、要素技術と管理技術の組み合わせからなるコア技術の重要性を知っていたのでしょう。90年前の西島亮二海軍技術大佐の先見性に感服するばかりです。
2.エンジニアは「小さく」できたことに誇りを持っていた
「大和」の建造に関わったエンジニアが誇らしく思ったこととは?
藤間氏の著作には、艦艇史研究の第一人者として数々の著作を残している元海軍技術少佐・福井静夫氏の言葉が紹介されています。
「私は戦後、こと最近においてまた、多くのわが国の青年諸君が、いな旧海軍の多くの年配の方がたまでが、ただ巨艦であるがために大和屋武蔵を誇りし、大和型を、わが海軍のシンボルのように思い込み、いたずらな礼賛をそれにそそいでいることに、あきたらなく思うものである。
(中略)さらに技術を、その設計と、工作の両面のみにかぎってみると、実は大和の誇りは、それが大きかったからではなく、それが小さかったことにあると、私は思っている。」(上巻p39)
意外な言葉です。大和は、全長約260メートル、幅約40メートル、排水量約7万トンという巨大な船体に、46cm主砲3基9門を搭載した、当時世界最大の戦艦でした。超弩級であることが強みと考えてしまいます。
しかし、エンジニアの立場では、他に負けない巨艦をいかにコンパクトに造り上げるか、ここに設計と製造のキモがあったようです。
自動車や家電、電子部品等々、考えてみれば、この「コンパクト化」はその後の日本のモノづくりの強みとなりました。その源流が、大和にあるのかもしれません。
そして、プロジェクトを主導した西島技術大佐はさらなるこだわりがあったようです。
3.早く、安く造る
当時の海軍内では「優秀な軍艦を与えられた予算内で予定竣工期に建造する」ことを強く要求されていました。一方、予算をオーバーすること、工期が遅れること、こうしたことが起きても仕方がないとする雰囲気もあったようです。
軍事技術には、経済性を無視しても、敵との戦いに勝つためのものとの大義があります。こうなると、性能第一主義が幅をきかすことになるのです。官僚主義、セクショナリズムがはびこります。いわゆる「親方日の丸」の意識が醸成されるのです。
したがって、能率を上げて、少しでも早く安くつくろうとする姿勢が生まれるはずがありません。「軍」という組織に所属していれば、こうなるのはしかたがないでしょう。
「宗教」、「軍」、「行政」、「政府」、「学校」という組織があります。歴史的に早い段階からある組織形態です。一方、私たちが所属する組織は「企業」です。前者に比べると歴史は浅いと言えます。そして、前者と後者には決定的な違いがあるのです。
市場の存在です。
企業は、市場の方を向いて仕事をします。市場が変わるのに合わせて、自分たちを変える組織です。変わらなければ、置いてけぼりを食らって、生き残れません。
ところが、「宗教」、「軍」、「行政」、「政府」、「学校」には市場はないのです。昨今、こうした組織の中にも、マーケティングの発想が求められる組織があるようですが、企業のそれとは事情が違います。
「宗教」、「軍」、「行政」、「政府」、「学校」という組織の目的は、自分たちの都合に合わせて組織を存続させることです。自分たちが変わるのではなく、外に変わってもらって組織の存続を図ります。したがって、当時の海軍内に「親方日の丸」の意識があっても不自然ではありません。普通のことです。
ところが、この「親方日の丸」の意識こそ、西島技術大佐がもっとも嫌ったものでした。前間氏は次のように表現しています。
(中略)(西島技術大佐は)現状になんら疑問をもとうとしない人間を、「ちょんまげを結って、下駄を履いたような奴を相手にしても話にならん」として相手にせず、もっぱら設備と生産システムを近代化して生産効率を高めることに懸命に取り組んだのである。(上巻p40)
こうした西島技術大佐のリーダーシップがあったらから、「1号艦「大和」の船体(船殻)建造に要した総工数は2号艦「武蔵」の半分だった」という成果がでました。現状を打破して改革を推し進めるのは現場ではなく、組織のトップ層です。
船体建造分の工期が同じなら職人の人数が半分、また、職人の人数が同じなら船体建造分の工期が半分です。船体建造分の人件費は、武蔵の半分と推察されます。
西島技術大佐には早く、安くつくるこだわりがありました。大和のすごさは、「小さく、早く、安く」つくったところにあるようです。
4.戦後の日本を先導した産業
戦後の日本は「技術大国」、「生産大国」への道筋を切り開きました。その先導役を果たしたのが造船業です。
終戦直後、軍需の消滅や賠償による厳しい制限下にありましたが、産学官の技術開発や政府の後押しで、造船業は活況を取り戻しました。
そして、1955年(昭和30年)には鋼船生産が戦前の約2倍となり、1956年(昭和31年)には建造量で世界一を達成。外貨獲得の主力となり「復興のシンボル」となったのです。
その後、「繊維→鉄鋼・機械→自動車・家電→電子部品・IT→高付加価値製造・サービス」と時代ごとに世界的な競争力と輸出を担う産業が交代してきました。ここで注目したいのは、先導役が「造船業」だったということです。
戦後の日本で造船業が最初のけん引役になったのは、大和を建造した海軍工廠やエンジニア、職人が持つ技術のお陰であったと容易に想像できます。ただ、そこで活かされたのは軍事技術ではなかったのです。
激しい受注競争がある商船の世界では経済性が重視されます。安価で短期間に建造できる技術が最大の要件です。親方日の丸の意識に基づく軍事技術はその対極にあります。
戦後の造船業で活かされたのは、西島技術大佐が独自に生み出した生産管理や生産システムだったようです。前間氏は次のように表現しています。
一般に、科学技術における新しい発明や発見、開発といったことは、劇的であるがゆえにわかりやすく、人々の注目を集めがちである。ところが、流れ作業化やコンピューター化といった生産システムの近代化はそうではない。
しかも、ジワジワと浸透していくものであるため、一つのシステムが完成するなでには時間がかかる。しかし、影響力は大きく、その成果は全産業へ広がっていく。しかも、一国の工業生産力、国際競争力を左右することになる。
西島が独自に生み出した生産管理および生産システムこそ、トヨタ生産方式に代表されるような、のちに世界を先導するまでに成長した日本的生産方式の源流となったのである。(上巻p40)
日本の強みは現場にあると言われてきました。個力に加えて、工程間連携を実現するチーム力が優れているのです。
さらに、仕組みとして生産管理の3本柱があり、個力、チーム力、生産管理、これらの体系を総合してモノ造り力と称します。
西島技術大佐が「早く、安く」造ることにこだわってくれたお陰で、そのノウハウが戦後に引き継がれたのです。造船業がグローバルで競争力を持つに至ったのにはそうした背景があったと言えます。
日本のモノづくりの源流が、意外なところにありました。仕組みの浸透は簡単ではありません。大きな改革にはトップのリーダーシップが欠かせないのです。そして、仕組みが浸透した時、波及する範囲はドンドン広がります。
5.生産量で把握する
前代未聞の複雑な巨大戦艦を建造するのです。生産計画と生産統制の仕組みがなければ、早く、安くつくるどころではありません。
ただ、当時の海軍工廠でも一定水準の管理はやっていたようです。工数管理を一応はやっていました。過去に建造した戦艦の実績はあるので、主要な工事の予定と必要な工数は設定できます。ただ実際には各職場担当者の勘と経験に頼った管理です。
・目で見たらここはちょっと人がだぶついているから人を減らそう
・ここは足りなさそうだから増やそう
こんな程度だったようです。計画VS実績による管理ではなく、成り行き管理、事がおきてから手を打つ事後対応になっていました。
親方日の丸の体質そのものです。何か問題があっても、予算が超過するのは当たり前とする風潮に侵されています。西島技術大佐は、そこにメスを入れたのです。
船体(船殻)建造の進み具合を客観的に把握するため「生産量」という考え方を導入しました。それまでは、仕事量を工数や金額だけで表示していたのです。下記のような感じした。
・ここの工程に必要な工数は●●●工数(人時)である。
ここから、ここまで溶接するとか、鋲を何本打つとか、隔壁を何枚固定するとか、ここからここまで塗装するとか、出来高としての「生産量」は評価していなかったのです。
したがって、上記に提示された、●●工数(人時)に見合った人数の職人を現場へ投入するだけです。その後は先述した、各職場担当者の勘と経験に頼った成り行き管理をやっていました。
過去に建造した戦艦の実績はあったのでそれを参考にすれば、ある程度の水準で予定通りにできるでしょう。
しかし、大和は前代未聞、実績のない巨大戦艦です。日程管理をする場合、出来高と工数の関係を明らかにする必要があります。出来高での「生産量」が分からないと、遅れの認識ができません。
そこで、西島技術大佐は次のように考えました。
「造船工事では多量生産と異なり、(工事の中身が複雑なことから)その生産量の把握が困難なために工数がとか金額で表示したり、計画したりしていた。
(中略)この工事は何工数かかるとか何円かかるといい、工事量があたかも工数や金額で表示されるような錯覚を起こしやすい表現が使用されていた。それが根本的な誤りである。(上巻p423)
生産量は、工事をその重量、数量(個数、枚数)、長さ、面積、容積等で表現せねばならない。(上巻p423)」
工程管理の観点にしたがった、的を射た見解です。建造工事でも生産量が正確に把握できれば、工数の制御が可能になり、能率(生産性)の良し悪しを判断できます。
生産性は、分母と分子の組み合わせで評価されます。それまでの海軍では、分母の工数しか追いかけていなかったわけです。分子の生産量がわかれば、生産性も評価できます。
船殻工事では、船鋲する鋲の総数は何本あるか、溶接ラインの全長はどれだけあるか、船体の水圧試験区画はいくつあるかが「生産量」です。
どれだけこなしたかを数えることによって、工事の進捗度を把握できます。時間当たりでこなす量が能率になるのです。能率を使えば、勘や経験によらない管理ができます。
西島技術大佐は大和の3万枚に及ぶ図面を一枚一枚丁寧に調べさせて、下記の数値を得ました。
・大和の船体に使われるリベット予定総数 6,090,072本 (実績6,153,030本)
・大和の船体でなされる溶接の長さ 347,564m (実際343,422m)
・水圧試験の区画数 1,682区画
リベット数600万本、溶接の長さ347km、このように船体建造での生産量を数値化したのが西島技術大佐です。数値になれば仕事量が実体感を持って現場へ伝えられます。
昨今の製造現場では当然のことです。ただ、納期遵守だけを追いかけて、受注案件をさばくだけの対応をしているので、横断的に捉えた工場の生産量を数値化できていない現場が、今もあります。生産量が数値化されなければ、生産性は評価できません。
6.西島カーブ、能率曲線
生産量が正確に把握できれば、工数の制御が可能になり、能率(生産性)の良し悪しを判断できます。
1)横軸に工程、縦軸に生産量
2)横軸に工程、縦軸に工数
これらが西島カーブ、能率曲線と呼ばれるグラフです。
これらのグラフを、工場別、職場別に準備して、計画VS実績を記入していきました。プロットした実績点が計画線から外れると遅れとして認識できます。この手法で西島技術大佐は工数管理をやったのです。
西島技術大佐は、遅れが認識された職場へ足を運び、現場と一緒になって、問題を解決していました。ただsに、計画から外れたことをやっているとカミナリが落ちたそうです。
客観的な根拠に基づいた西島技術大佐の仕事ぶりは、現場から信頼を得ていました。西島技術大佐の部下である木下共武技術少佐の言葉が「リーダーシップとは何か」を教えてくれています。
西島さんが現場をまわるときがこわいのです。現場の技手などは、われわれが行っても屁とも思っていないが、西島さんがくるとなるとピリピリしている。
なぜなら、各職場から上がってくる曲線に目を通して、だいたいここらあたりがおかしいとめぼしをつけてから現場にやってくるからです。
ただやみくもにまわっているのではない。だから、西島さんは威張るわけじゃないが、言われることはごもっともとなる。そのため、現場のベテランである技手や工長たちも西島さんにだけは心腹していた。 (上巻p425)
能率曲線、西島カーブ、それ自体に新鮮な驚きはありません。日程計画の数量管理手法で流動数曲線がありますが、それと同じです。さらには横軸に工数、縦軸に生産量のグラフを描けば、その傾きが人時生産性になります。
私達は、今、ITツールを使って、手軽に処理ができるのです。しかし、90年前にはそんなツールはありません。方眼紙に、手書きで、一枚一枚描いて、管理していったのです。
手書きのグラフで現場を管理している西島技術大佐の仕事ぶりを目に浮かびます。何か感じるものがあるのではないでしょうか?
現場の工員にとって西島技術大佐はこわいけれども話の分かる主任だったのです。
中小製造現場でのモノづくりの本質として、作業者の協力を得ることは欠かせません。「工場経営の本質は他人の力を借りて経営者の想いを実現することにある」以上、そうする必要があります。そして、それはトップのリーダーシップ次第です。
トップは現場が納得できる客観的なデータを示して、協力を引き出します。闇雲な精神論だけで人は動かないのです。
90年前の大和の建造現場で、西島技術大佐は、そうした科学的な姿勢で現場に向かい、成果を出しました。これは、中小製造経営者にも当てはまります。
