戦略的工場経営ブログ価格転嫁を実現させる行動をしているか?
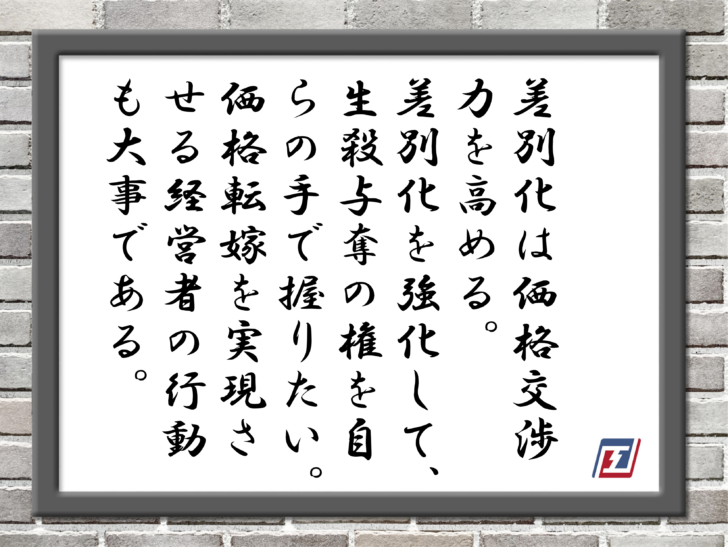
中小企業白書2024年版は、生産性を高める取り組みとして、販売する製品の価格アップをお客様へ働きかけることも重要であると指摘しています。
下記は大企業と中小企業の売上高営業利益率の推移です。1990年、2008年、2022年、3年間の推移です。
●売上高営業利益率の推移
(1990年・2008年・2022年の順、2008年にリーマンショック)
大企業 4.2% 2.7% 6.3%
中小企業 2.9% 1.2% 1.9%
資料:財務省「法人企業統計調査年報」
(注)ここでいう大企業とは資本金10億円以上、中小企業は資本金1億円未満の企業とする。
大手はコロナ禍で傷ついた収益力を回復させています。30年前と比べて利益率は高いです。一方、中小企業の現在の営業利益率は30年前よりも落ちています。
就業者の7割は中小企業に所属しているのです。日本の生産性が上がらない背景が営業利益率の推移にも表れています。中小企業は儲かりにくい状況にあるのです。
さらに、下記は大企業と中小企業の売上原価率の推移です。1990年、2008年、2022年、3年間の推移です。
●売上原価率の推移
(1990年・2008年・2022年の順、2008年にリーマンショック)
大企業 83.4% 82.1% 78.8%
中小企業 77.7% 73.8% 68.3%
資料:財務省「法人企業統計調査年報」
(注)ここでいう大企業とは資本金10億円以上、中小企業は資本金1億円未満の企業とする。
大手も中小も売上原価率が低下しています。
売上原価率は材料ロス削減や作業効率向上で低減できるものです。現場の改善活動や生産工程の自動化、情報システムの導入などの成果と考えられます。
同じ売上高を得るための製造費用が30年前よりも低く抑えられているので、大手も中小も生産性を高める努力をしている・・・・と言うことはできそうです。
営業利益率は上がらないものの、生き残りをかけて頑張っている中小の姿が、売上原価率の変化に見て取れるのです。ただし、ここには中小が直面するビジネス上の厳しさもあらわれています。
中小製造企業のビジネスモデルの多くは下請け型です。この場合、中小の価格は、大手にとって原価です。大手の売上原価率が低くなっているということは、そこへ部品を供給する中小の価格は上がりにくいことも意味します。
さらに、下記は大企業と中小企業の労働分配率の推移です。1990年、2008年、2022年、3年間の推移です。
●労働分配率の推移
(1990年・2008年・2022年の順、2008年にリーマンショック)
大企業 57.8% 63.1% 51.2%
中小企業 73.4% 82.0% 79.2%
(注)大企業は資本金10億円以上、中小企業は資本金1億円未満の企業について集計したもの。また、各項目・指標の算出は以下のとおり。
労働分配率=人件費÷付加価値額。
付加価値額=人件費+支払利息等+動産・不動産賃借料+租税公課+営業純益。
人件費=役員給与+役員賞与+従業員給与+従業員賞与+福利厚生費。
大手の労働分配率は50%前後まで下がっている一方、中小は70~80%前後で推移しています。
利益と人件費の原資は付加価値額です。数値にも表れているように、中小では、従業員の給料を増やす余力は、大手ほどありません。
コスト削減は大事ですが、それ以上に大事なのは、付加価値額の積み上げです。中小製造企業の持続的な成長のためには、付加価値額の積み上げが欠かせません。
したがって、人時生産性向上を目指して、価格を上げることも考えたいのです。中小白書2024年版では、価格交渉の重要性について解説しています。
1.価格交渉の状況
2.各コスト変動に対する価格転嫁率の推移
3.価格協議の実施状況別によるコスト変動分の価格反映状況
4.差別化状況別に、コスト変動分の価格反映状況
出典は全て中小白書2024年版です。
1.価格交渉の状況
下記は、中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」を用いて、2023年3月と2023年9月における価格交渉の実施状況を数値化したものです。
・価格交渉を希望したが、交渉が⾏われなかった
・発注企業から、交渉の申し入れがあり、 価格交渉が⾏われた
これらに該当する企業の割合を示しています。
●2023年3月と2023年9月における価格交渉の実施状況を見たもの
2023年3月(n=20,722)
価格交渉を希望したが、交渉が⾏われなかった 17.1%
発注企業から、交渉の申し入れがあり、 価格交渉が⾏われた 7.7%
2023年9月(n=44,059)
価格交渉を希望したが、交渉が⾏われなかった 7.8%
発注企業から、交渉の申し入れがあり、 価格交渉が⾏われた 14.3%
これを見ると、「価格交渉を希望したが、交渉が行われなかった」と回答した割合は17.1%から7.8%に低下しています。一方で「発注企業から、交渉の申入れがあり、価格交渉が行われた」と回答した割合は7.7%から14.3%に上昇しています。
従来に比べて、価格交渉をやっている企業が増えているようです。原材料費をはじめとする諸物価高騰などを背景に、価格交渉をお願いしやすい状況になっています。あとは経営者の行動次第です。
2.各コスト変動に対する価格転嫁率の推移
下記は、2022年3月と2023年9月における、各コスト変動に対する価格転嫁率の推移です。価格転嫁率は「仕入価格の上昇分を販売価格に転嫁できている割合」です。
原材料費、労務費、エネルギー費でコストが上がった分のうち、どれだけ価格転嫁ができているか?これを見てみます。
●各コスト変動に対する価格転嫁率の推移
2022年3月(n=25,575)
原材料費 44.2%
労務費 32.3%
エネルギー費 32.4%
2023年9月(n=44,059)
原材料費 45.4%
労務費 36.7%
エネルギー費 33.6%
資料:中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」
(注)2022年3月、9月、2023年3月、9月の調査における、価格転嫁率の平均値を算出したもの。主要な発注側企業(最大3社)との間で、直近6か月のコスト上昇分のうち、何割を価格転嫁できたかの回答について、発注側の企業ごとに名寄せ・単純平均したもの。
これを見ると、2022年3月から2023年9月にかけて、いずれのコスト要素も価格転嫁において、改善傾向にあるようです。各コストの価格転嫁率が高まっています。ただし、十分な価格転嫁ができているとはいえません。
白書では、価格交渉の取組強化が課題であると指摘しています。理解が得られやすいと思われる原材料費の価格転嫁でさえ、半分程度に留まっているのです。残り半分を、さらなるコスト削減か価格転嫁で埋めないと、その分、我が社の儲けが減ってしまいます。
3.価格協議の実施状況別によるコスト変動分の価格反映状況
下記は、「令和5年度取引条件改善状況調査」を用いて、価格協議の実施状況別に、コスト変動分の価格反映状況を数値化したものです。価格交渉をやろうとする行動は価格移転につながるのか?これを見てみます。
ここでは、全て反映された(100%)+概ね反映された(99~81%)+一部反映された(80~41%)の割合を「反映された」、あまり反映されなかった(40~1%)+反映されなかった(0%)の割合を「反映されなかった」としています。
●コスト変動分の価格反映状況(価格協議の実施状況別)
反映された/反映されなかった
協議実施(n=11,155) 87.8%/12.2%
協議非実施(n=6,553) 50.7%/49.3%
これを見ると、協議を実施している企業は、協議を実施できていない企業と比べて、より高い水準で価格転嫁をやれています。
十分な価格転嫁を実現するためには、まず、価格転嫁に関する協議の場を設けることです。交渉の場を持てば、価格転嫁できる可能性は高くなります。あとは経営者の行動次第です。
4.差別化状況別によるコスト変動分の価格反映状況
下記は、自社の製品・商品・サービスに関する競合他社との差別化状況別に、コスト変動分の価格反映状況を見たものです。自社製品の差別化要因は価格転嫁に貢献するのだろうか?これを見てみます。
ここでは、全て反映された(100%)+概ね反映された(99~81%)+一部反映された(80~41%)の割合を「反映された」、あまり反映されなかった(40~1%)+反映されなかった(0%)の割合を「反映されなかった」としています。
●コスト変動分の価格反映状況(競合他社との差別化状況別)
反映された/反映されなかった
大いに差別化できている(n=2,058) 84.8%/15.2%
やや差別化できている(n=7,760) 79.0%/21.2%
あまり差別化できていない(n=3,933) 69.7%/30.3%
全く差別化できていない(n=798) 48.7%/51.2%
差別化要因を持っている企業は、価格転嫁も進む傾向にあるようです。差別化も、価格交渉力を高める要点と言えます。
価格転嫁は、我が社の事情で言っているだけです。お客様にとっては、価格の引き上げにしかすぎません。そうであるなら、自社の製品・商品・サービスが、価格引上げに見合った価値を提供できていなければなりません。
「おたくの製品はあそこよりもイイですよね。」という言葉をお客様から引き出せなければ、価格アップ交渉は難しくなります。お客様は貴社と競合先を比べるからです。
差別化は価格交渉力を高めます。差別化を強化して、生殺与奪の権を自らの手で握りたいのです。価格交渉に挑む経営者の強い行動も大事です。
