戦略的工場経営ブログこだわり消費時代は尖った製品やサービスで勝つ
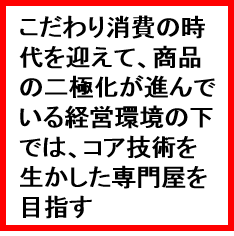
尖った製品やサービスを開発する仕組みを作りませんか?。
1.二極化
「おたくは何屋さんですか?」と問われた時に、一言で答えられますか? 価格競争を回避したかったら、顧客目線です。 さらに「モノ」ではなく「コト」の提供から新たな製品や技術を開発を考えます。 そうして、新たな顧客、新たな市場を生み出さなければなりません。 網羅的な事業展開では顧客に選ばれるのは難しいです。 尖った専門性を高める事業展開になります。 株式会社カカクコムの田中実社長は消費者の価格志向に関して下記のように語っています。 同社は価格比較サイトを運営しています。やはり二極化が続いている。 例えば40万円するデジタルカメラや 欧米の高級家電などが 信じられないスピードで売れており、値段も下がらない。 個人的に自動車が好きなので 最近限定モデルを購入したが、すぐに完売し、半年たっても納車されない。 一方で水やおむつ、清涼飲料などいつでも買える日常的な商品への価格志向は強い。 デフレとインフレが同居している印象だ。2極化は避けられない社会現象です。 例えば、少子化で人口が減る中、首都圏に集中しつつある人の流れがあります。 10人にひとりが東京の人です。 そして、4人にひとりは東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)です。 (地域から生まれる新たな資本主義) つまり、地方と都市部での格差の拡大が懸念されます。 人材、所得、教育、各種サービス・・・。 ピンとキリの差がドンドン広がっています。 かっての日本には「中流意識」がありました。 正規分布の中央に属している感覚です。 多くの人が自分の所得や生活水準は世間並であると考えていました。 造れば売れる時代、イケイケドンドン。 かいた汗の量だけ、確実に給料も増えていました。 そうした「中流階級」が、今、消滅しつつあります。 一昔前なら、中間層向けに”無難な”製品を造っても、そこそも売れました。 その結果、乗り遅れる企業も少なく、業界全体も伸びていたわけです。 それが、平成バブルが崩壊し、1990年代の前半から外部環境が変化し始めました。 価格が高いモノと低いモノ。 売れるモノと売れないモノ。 儲かるモノと儲からないモノ。 市場で明確に選別されます。 その結果、中小製造業でも収益性の高い企業と低い企業でのバラツキが広がっているのです。 ここでも2極化が進んでいます。 市場の不確実性が高まる中、高収益率を達成する企業とそうでない企業との格差は拡大しています。 1980年代対比、2000年代以降で、その傾向は顕著です。 (付加価値を拡大し続けるためには絶対に○○が必要) 価格が高いモノと低いモノ。 売れるモノと売れないモノ。 貴社の製品は、どちらに分類されますか?(出典:日経新聞2016年3月21日)
2.専門屋
さらに、カカクコムの田中社長は次のようにも語っています。家電メーカーは中国や台湾の企業との価格競争に巻き込まれて苦戦した。 開発力が低下したのか、欲しい商品が出てこない。 今はこだわり消費の時代だ。 トースターや掃除機、洗濯機など単一商品に特化したメーカーがどんどん出ている。 ポータルサイトも総合的な内容では勝てず、特定の分野に強いサイトが優位になる。(出典:日経新聞2016年3月21日)
 ”尖った”メーカーが生き残ります。
特徴がなければ価格競争に巻き込まれます。
中小製造企業は体力を消耗し消えていくだけです。
中小製造業が絶対に回避すべきは価格競争です。
商品の価格決定権を自ら持つ事業展開を目指すのが存続と成長のカギです。
高付加価値化で欠かせないのは、お客様視点です。
「コト」に着目すること。
「コト」を創出するということは、新たな市場を生み出すコトと同じです。
価格競争を回避できます。
(高付加価値化で必要な「コト」を探る○○主義とは)
”尖った”商品こそが、こだわり消費時代にマッチした商品です。
今や消えつつある中流階級向けの商品開発に経営資源を振り向けてはなりません。
価格競争に陥って動きが取れなくなります。
大手とは一線を画するモノづくり戦略が必要なのです。
目指すは、コア技術を生かした”専門屋”。
製品でもサービスでも、特化した技術を磨き上げます。
出る杭を目指します。
そもそも、中小製造業の経営資源には限りがあります。
一点突破主義経営は中小の現場がとるべき戦略なのです。
中小の強みである柔軟性や機動性を生かせます。
どのような分野に特化すれば、”尖った”製品やサービスを提供できるのかを考えます。
貴社の強み、コア技術を大いに生かすのです。
大手がまねできない、中小ならではアイデアで、持続的な競争優位性を築きます。
「おたくは何屋さんですか?」と問われたときに、一言で答えられるようになっています。
尖った製品やサービスを開発する仕組みを作りませんか?
株式会社工場経営研究所 「儲かる工場経営」メルマガ ご登録ください。
毎週火曜日配信中。
https://48auto.biz/koujoukeiei/registp.php?pid=3
”尖った”メーカーが生き残ります。
特徴がなければ価格競争に巻き込まれます。
中小製造企業は体力を消耗し消えていくだけです。
中小製造業が絶対に回避すべきは価格競争です。
商品の価格決定権を自ら持つ事業展開を目指すのが存続と成長のカギです。
高付加価値化で欠かせないのは、お客様視点です。
「コト」に着目すること。
「コト」を創出するということは、新たな市場を生み出すコトと同じです。
価格競争を回避できます。
(高付加価値化で必要な「コト」を探る○○主義とは)
”尖った”商品こそが、こだわり消費時代にマッチした商品です。
今や消えつつある中流階級向けの商品開発に経営資源を振り向けてはなりません。
価格競争に陥って動きが取れなくなります。
大手とは一線を画するモノづくり戦略が必要なのです。
目指すは、コア技術を生かした”専門屋”。
製品でもサービスでも、特化した技術を磨き上げます。
出る杭を目指します。
そもそも、中小製造業の経営資源には限りがあります。
一点突破主義経営は中小の現場がとるべき戦略なのです。
中小の強みである柔軟性や機動性を生かせます。
どのような分野に特化すれば、”尖った”製品やサービスを提供できるのかを考えます。
貴社の強み、コア技術を大いに生かすのです。
大手がまねできない、中小ならではアイデアで、持続的な競争優位性を築きます。
「おたくは何屋さんですか?」と問われたときに、一言で答えられるようになっています。
尖った製品やサービスを開発する仕組みを作りませんか?
株式会社工場経営研究所 「儲かる工場経営」メルマガ ご登録ください。
毎週火曜日配信中。
https://48auto.biz/koujoukeiei/registp.php?pid=3
